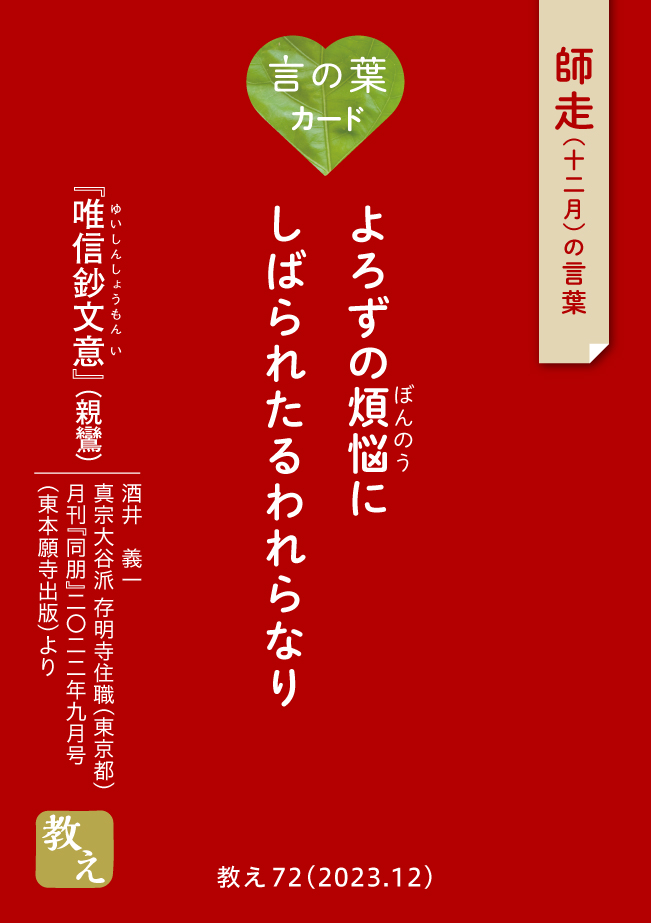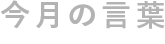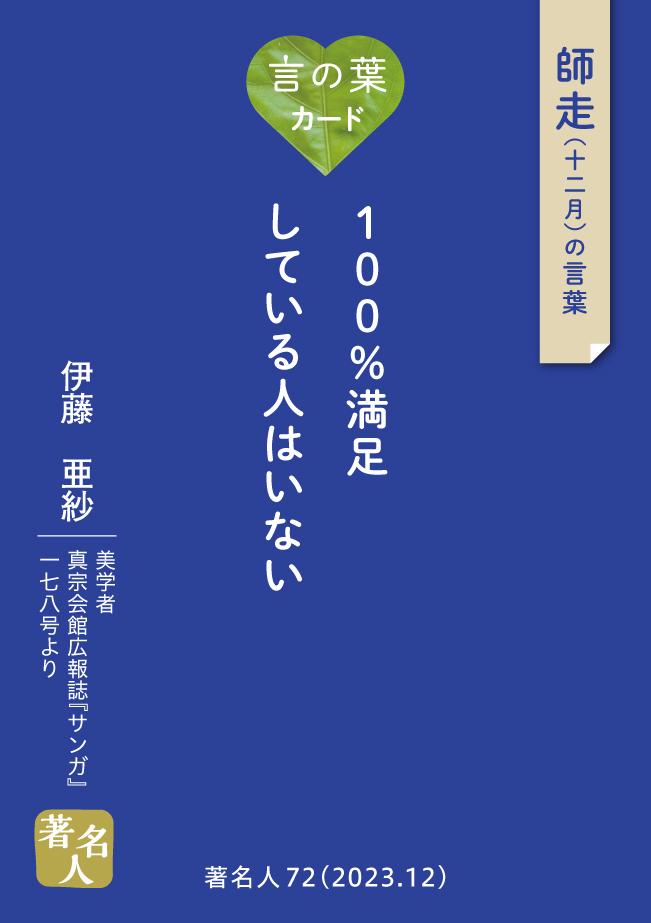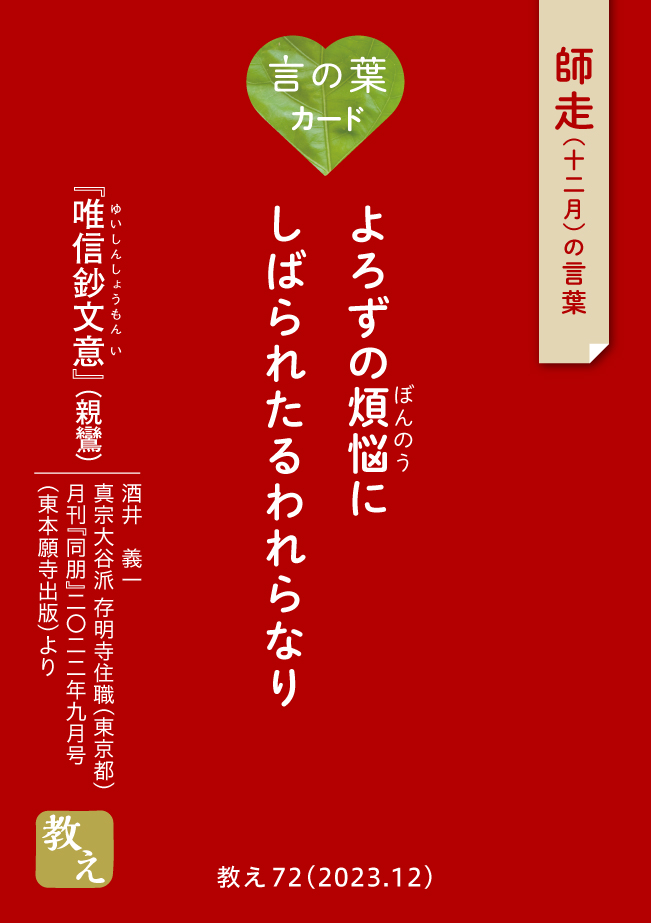
コロナという時代を迎え、不登校の小中高生は過去最多の19万人に、という報道があった。今、時代社会そのものが大きな闇を抱えている。
子どもと関わることを大切にしてきたお寺の活動の中でも、不登校ということについて今まで保護者から相談を受けてきた。しかし、実際にその人と出会い、話を聞くということはとても難しいこと。彼ら・彼女らの辛さは、なかなかわからないものだ。
親鸞聖人は、当時、具縛(ぐばく)の凡愚(ぼんぐ)や屠沽(とこ)の下類(げるい)と呼ばれていた人々と出会い、こう言われた。
よろずの煩悩(ぼんのう)にしばられたるわれらなり
これは、それらの一人ひとりとていねいに出会い、きちんと話を聞いた人でなければ出てこない言葉なのだろう。さまざまな煩(わずら)いや悩(なや)みにがんじがらめになっている人々の、具体的な現実を知り続けられたのだろう。
さらにそのすがたを他人事とせず、自分もその中の一人だと、すなわち「われらなり」と受け止められた。
ここに、「ひとりと出会う ともに生きる」という親鸞聖人がおられる。
私もそのような生き方を実践したい。
『唯信鈔文意(ゆいしんしょうもんい)』(親鸞)
酒井 義一氏
真宗大谷派 存明寺住職(東京都)
月刊『同朋』2022年9月号(東本願寺出版)より
教え 2023 12


もともと仏教語だった「愛嬌(あいきょう)」は、現代語としても使われています。仏教語としては「愛し敬うこと。仏・菩薩(ぼさつ)の優しく温和な相貌(そうぼう)」を表しますが、現代語では「女性や子供などが、にこやかでかわいらしいこと」(『広辞苑』)に用いられます。だから「あの子は愛嬌がある」などと言えば、「あの子は人なつこく可愛らしい」という意味で理解できます。「愛嬌」と似た意味の言葉として「和顔愛語(わげんあいご)」があります。これは「やわらかな顔と、優しい言葉」の意味で、阿弥陀(あみだ)さんが人間に示される関わり方です。阿弥陀さんは、人間に対して、一方的に片思いをされている仏さまなのです。
人間は、自分を一番愛しているように見えて、状況が変われば、自分を見捨てる生き物でもあります。ひと昔前の川柳に、「亭主殺すにゃ刃物はいやぬ。役に立たぬと言えばよい」というのがありました。定年退職後の老夫婦が、夫婦喧嘩をしたときの情景を詠んだ川柳です。奥さんが旦那さんに向かって、「あんたは役立たずだ」と言えば、旦那さんはぺしゃんこになったというのです。なぜぺしゃんこになるかと言えば、旦那さんは「役に立つこと」を自分の誇りにしていたからです。それなのに定年退職で、毎日家でゴロゴロしていたのでは、何の役にも立っていない。役に立たないものは意味がないと自分で自分を悲観したのでしょう。
これはご夫婦の話ばかりではありません。現代社会を覆っている価値観は、「役に立つか、立たないか」です。そして「役に立たないものは、存在の意味がない」と自らのいのちを苦しめることにもなってしまいます。そんな人間に対して、阿弥陀さんは「和顔愛語」で寄り添って下さいます。あなたは「役に立つか、立たないか」という価値観で自分を切り刻んでいるけれども、そんな価値観は幻想だと優しく教えて下さいます。そして、「役に立っても、立たなくても」私の子どもとして一方的に愛して下さるのです。いい子にしているから愛して下さるのではありません。いい子も悪い子も、同じように愛して下さるのです。
武田 定光氏
真宗大谷派 因速寺住職(東京都)
仏教語 2023 12


「一番あやしいのは自分じゃないか。」
街角の「あやしい人を見たら110番」の看板を見て、K先生が笑いながら言われた。人を善し悪しと決めつけ、全能の審判者になったつもりで評価を下している自分があてにならない。
「天下におのれ以外のものを信頼するよりはかなきはあらず。しかもおのれほど頼みにならぬものはない。どうするのがよいか。森田君、君この問題を考えたことがありますか。」
夏目漱石(1867-1916)が弟子の森田草平(1881-1949)にあてた手紙の一節である。近代日本の知性を代表する漱石のするどい人間観察だ。その漱石でも脇の甘さが残る。「どうするのがよいか」と問いかけるところに、まだ自分の知性、能力をたのむ心が尾をひいている。愚かな身に着地しきれていない。
しかし、わかったふうに漱石を責めることはできない。客観的な自分を見ることほど困難なことはない。
親鸞は、そのようなどうすることもできない愚かな身を「煩悩具足(ぼんのうぐそく ※)の凡夫(ぼんぶ)」と言い当てた。仏の「摂取不捨(せっしゅふしゃ ※)」の愛を信じて、凡夫の事実に身をまかせれば、少しは自由でのびのびとした世界がひらけてくるのではなかろうか。
現代の病は、凡夫であることを封じこめるところにある。いつも正解を求め、間違わない者、義(ただ)しい者でなければならないと、自分で自分自身を追いこめるところに窮屈さがある。
北陸の真宗門徒の間に言い習わされてきた言葉がある。
「凡夫のはからい、ぬかりがある。」
- 煩悩具足
- 様々な煩悩をすべてそなえて生きていること
- 摂取不捨
- どのような存在もおさめとって見捨てないということ
狐野 秀存氏
大谷専修学院 前学院長
真宗会館広報誌『サンガ』168号より
法話 2023 12

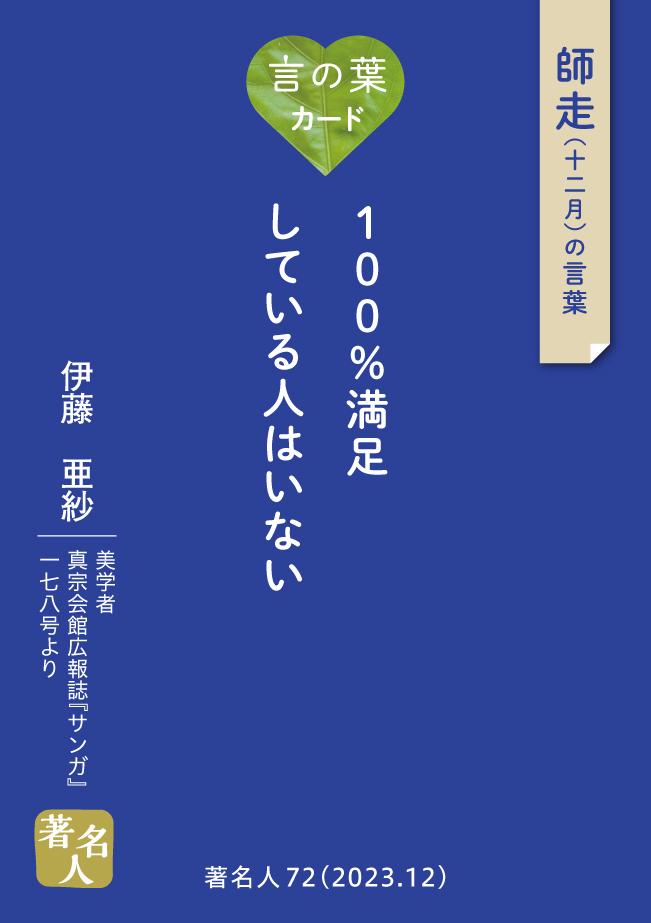
私自身、吃音(きつおん)を持っているのですが、「言葉を発する」という行為一つとっても、私たちの体は意識していないところで、すごく複雑なプロセスを自然に行なっているんですね。障害を抱えた人たちにお話を聞いていくと、一人ひとりがまったく違う、そういう言わば「究極のローカルルール」を生きておられるということが分かってきました。例えば視覚障害を持った方と待ち合わせをするときに、駅からの道のりをメールで教えてくれたりするんですが、その書き方が、ちょっとした段差とか、そこだけタイルの材質が違うんだとか、見えている私と全く違うものを目印にされているんです。その方と一緒にいると、同じ町でも、まったく違う場所のように見えてくるようで、すごく面白いんですね。
そもそも自分の体に100%満足している人っていないと思うんです。社会のなかで変えるべきことはまだまだたくさんありますが、それでも究極的にはたまたま与えられたこの身体を引き受けて生きていくしかない。だから障害について考えることは、思い通りにならない自分と向き合っていくことでもあると思うんですね。
障害の有無に関わらず、今は自分を認めることがとても難しい時代ですよね。若い方でも「いいね」の数とか、フォロワー数とかで評価されてしまって、自分を商品のように考えてしまう人も多いんじゃないでしょうか。でもその自分は、世界に一人しかいない。本当は数字に変換できないものだと思うんです。
障害のある人たちと関わっていると、肩を貸したり手を引いたり、身体的な接触が増えるんですね。その時のコミュニケーションって、普段のものと何かが違うんです。いつもは視覚優位で、相手の情報を一方的にキャッチしようとしている。距離をとって、無意識に相手を評価するような態度を取っているんです。でも触覚的なコミュニケーションって、それとは全く違うルールで動いていることに気がついたんです。そこに注目して書いたのが『手の倫理』という本でした。
伊藤 亜紗氏
美学者
真宗会館広報誌『サンガ』178号より
法話 2023 12