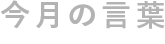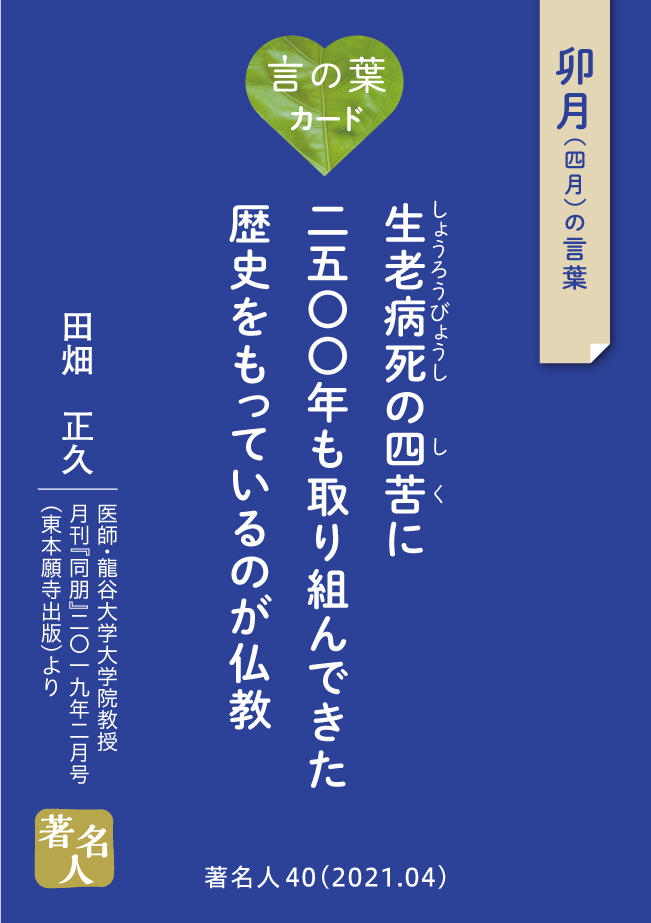お釈迦さまが自らの青年時代のことを回想して述べたことの中に、「三つのおごり」というものがあります。「若さのおごり」「健康のおごり」「生命のおごり」という三つのおごりたかぶりで、人間の本質的なものです。私は若い・元気で健康だ・死を忘れて生きているということは、若くて役に立ち、健康で誰の世話にもならない、まわりにも頼りにされていることを善しとし価値がある生き方だと執着しているものは、逆に老いること、病になること、死ぬことは、価値のないもの、無意味なものだと自分や他者を認識することになります。執着が自他を軽んじ苦しめていることに無自覚なのだと教えています。
ある法話を聞く会に、毎回身を運んで来られていた九十歳のおばあさんに、お話の感想をお尋ねしようとそばに座ると、横におられたお嫁さんが、「おばあさんは耳がもうまったく聞こえないのです」と言います。
ある時、いつものように一番前で聞いておられたおばあさんは私に、「念仏によって居場所をいただいております」と一言おっしゃいました。九十年の身が、善し悪しの意識、人間のものさしを超えて念仏を選び取って生きる、お仲間の方々とともに教えを聞く場に身をおかずにはおられない姿があります。
思い通りになることしか善しとして受け入れることができないという執着の意識が照らされて、どこまでもこの世を捨てず、この世に在って如来(にょらい)の呼び声とともに生き尽くされている、私たちの前を歩まれている姿としていただかれます。
『ブッダの教え』
河野 通成氏
真宗大谷派 緑芳寺住職(大分県)
『僧侶31人のぽけっと法話集』(東本願寺出版)より
教え 2021 04


「甘露」は飴の名前で有名ですが、もとは仏教語です。原語の意味は「不死」や、「神々が常用した不死を与える飲料」などで、古代中国では、天下泰平の瑞祥(ずいしょう)として天が降らせる甘いつゆを意味したようです。しかし、仏さまの説法は決して「甘い」ものではありません。人間が逃れることのできない「老・病・死」という現実を突き付けます。それがどうして「甘露」なのでしょうか。それは厳しい現実を、阿弥陀(あみだ)さんの慈悲に溶かされることにより、それをいただく人間が「甘露」のようだと受け止めたのでしょう。それは味覚の甘さではなく、まさに仏法(ぶっぽう)の味わい深さを譬喩(ひゆ)的に表現したのです。
話は変わりますが、以前、「仏さんとは何だ」と尋ねられたことがありました。それはお父さんの四十九日法要を勤(つと)めた息子さんからの問いです。息子さんは生前のお父さんとは折り合いが悪かったのです。ところが、四十九日法要を勤めたときに、息子さんから、「生きているときには親爺とうまくいかなかったし喧嘩もした。しかし、この頃は、親爺と喧嘩したこととか思い出せないんですよ」と聞かされたのです。そこで私は「仏さんとは、姿かたちは見えないけれども、そうやってお父さんとの諍(いさか)いや怨みを、スーッと取り去ってくれるものではないですか」とお話しました。
生前は親子共々に「煩悩(ぼんのう)」が邪魔をして、上手くいきません。しかし、どちらかが亡くなり人間から仏さんに変わると、「煩悩」が浄化され、まさに「甘露」の味わいへと変化していくのでしょう。
武田 定光氏
真宗大谷派 因速寺住職(東京都)
仏教語 2021 04


四月八日はお釈迦さまのお誕生日・花まつりです。全国各地のお寺や、仏さまの教えをいただく学校などでは、お釈迦さまの誕生された姿・誕生仏に甘茶をかけたり、白い象をひっぱったりと、お釈迦さまの誕生をお祝いする行事が行われます。
日本では、桜の花が咲く季節と時を同じくして、花まつりの季節がやってきます。桜の花の美しさは、あっという間にその花びらが散ってゆくその儚(はかな)さと相まって、私の心に響いてきます。
「散る桜 残る桜も 散る桜」。これは、江戸時代の僧侶・良寛さんが遺された句です。「散る桜 残る桜も 散る桜」、一見華やかな春の季節にあって、自分自身の命を桜の花の儚さに重ねる、見事な句です。
花まつりはお釈迦さまの「誕生」をお祝いする行事ですが、仏さまの教えに照らされてみると、人間の誕生は生まれた瞬間から、死を背負っています。桜の花が、咲いた瞬間から、やがて散りゆく命を生きているのと同じです。
生まれた瞬間から、私たちは「老病死」という現実を背負って生きていくことになります。生まれた瞬間から、老いつつある身を、縁が催せば病を生じる身を、そしてどんな人であっても、一切の人びとが、やがて命を終えていかなければならない、「この身」を生かされています。
花まつりといえば、子どもたちのための行事だと思われがちですが、この「生死一如(しょうじいちにょ)」の人間の身の事実を、お釈迦さまの誕生をとおして教えられる花まつりは、老いも若きも関係なく、私が「人と生まれた」ことを確かめる、そういった機縁なんでしょう。
松田 亜世氏
真宗大谷派 企画調整局参事
「いま、あなたに届けたい法話Ⅰ」(しんらん交流館)より
法話 2021 04

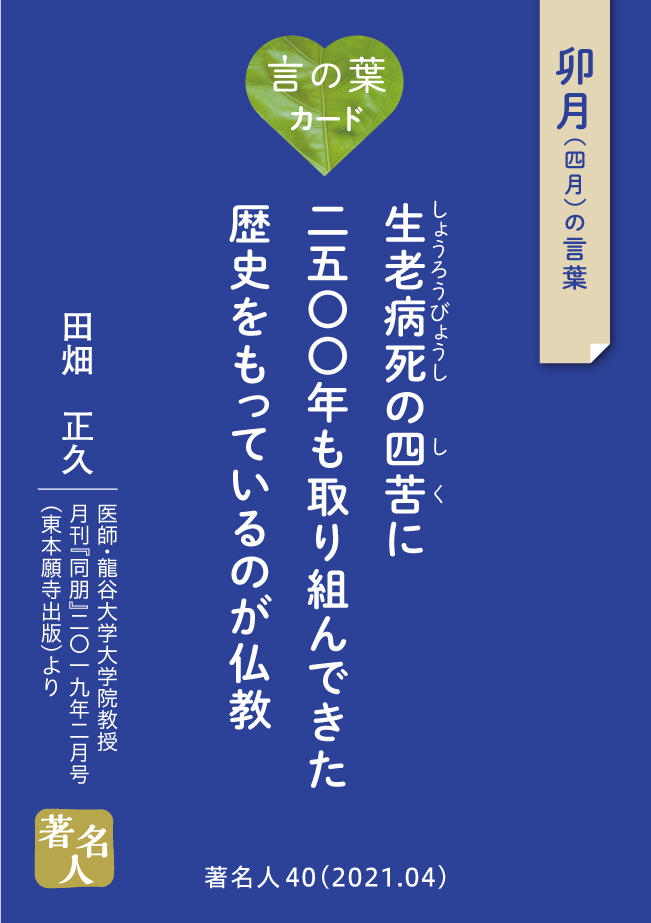
かつて秋月龍珉(あきづきりょうみん)という禅宗の僧侶が、埼玉医科大学という医療系の大学で教授をしておられた時、講義の中でこんな話をされたそうです。〝皆さんがこれから医療の世界で仕事をすることは、人間なら誰一人逃れられない生老病死(しょうろうびょうし)という苦しみに関わっていくことになる。その生老病死の四苦(しく)に2500年も取り組んできた歴史をもっているのが仏教だ。つまり医療と仏教は同じ課題に向き合っているのだから、医療に携わる者は仏教の素養をもってほしい〟と。
私はその言葉を本で読んで、とても勇気づけられました。なぜなら、それまで別のことと思っていた聞法(もんぽう)と医者としての仕事が、同じことを課題にしていると知らされたからです。その言葉に励まされて、医療と仏教というふたつのことにずっと関わり続けることができたのだと思います。
本当に人間を救うのは、医療ではなく仏教だと思っていた―。
私がまだ現役の外科医だった頃の話です。大腸ガンの患者さんの手術を執刀し、その後5年間ほど経過を観察した結果、再発の兆候が見られなかったため、「もう大腸ガンの心配はありませんよ」とお伝えして、かかりつけの開業医の先生に後をお任せしました。ところが、その2年後に、その患者さんが病院へ戻ってこられたのです。黄疸(おうだん)で全身が黄色くなった状態で…。調べると、新たにできたすい臓ガンが肝臓に転移し、もう手のほどこしようのない状態で亡くなられたのです。
その時、本当に一人の人間を救うのは医療か仏教かと考えたんです。医療は結局、その方が老病死につかまるのを5年か7年ほど遅らせただけでした。こういう場合、医療は常に敗北に終わるわけです。それに対して仏教は私たちに〝生死を超える道〟を示してくれます。生死を超えたらどうなるのか。「人間に生まれてよかった、生きてきてよかった」と人生を生き切っていける可能性が開かれるのです。
田畑 正久氏
医師・龍谷大学大学院教授
月刊『同朋』2019年2月号(東本願寺出版)より
著名人 2021 04