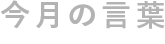自らの命が永遠でないことは誰もが知っています。また、それがいつおとずれるとも知れないものであることも誰もが承知しています。ですから、清沢先生(※)のこの言葉に初めて接した時の私の印象は、「そんなことはあたり前ではないか」というものでした。ですが、私自身の日常は、日頃から死とともにある生を自覚しているかというと決してそうではなく、むしろ、死を遠い未来のことと考え、死から目を背けて生きていると言わねばなりません。
私自身の日常の意識は、どこまでも生と死を対立することとして捉(とら)え、生に執着(しゅうじゃく)し、死を厭(いと)い避けようとして生きています。ですから、死を身近に感じる出来事に遭遇(そうぐう)したり、死の不安をともなうような病気になると、死の恐れの前で動揺し、苦しむことにもなります。
清沢先生は、仏教によって生と死とを相反(あいはん)することと認識しているうちは本当の安らぎに立つことはできないと述べます。なぜなら死の不安はどこまでも生に執着し死を避けたいと思うことから生じるからです。この執着から解放されていく道を説く仏教を人生の依り処(よりどころ)とし、生も死もひとしく縁によって起こる事実であり、縁によって生まれ、生き、死んでいく自らの身の事実を受けとめることなくして、本当の安らかさはないと確かめていきます。
しかし正直なところ、その道理をあきらかにし、認識できたとしても、その身の事実を受けとめて生きることは、実際には困難であると言わざるを得ません。それは、生と死を含め自らの人生の内容をどこまでも自らにとって好ましいことか否か、都合の良いことか否かという相対的な価値判断で受け取ることを一歩も離れることができない者が私であるからです。このような私たちのあり方を悲しみおこされたのが阿弥陀仏(あみだぶつ)の本願(※)に他なりません。
生と死を人生の内容としてあわせもつその私が、どのような状況にある生も、どのようなおとずれ方をする死をも包んで、自らの一生をかけがえのないこととして受けとめて生きていく、そういう深い願いが満たされていく生き方が本願念仏の仏道に恵まれることを、清沢先生は思索し、語っていかれたのだと思います。
- 清沢満之(1863~1903)
- 明治期に活躍した仏教者、哲学者、教育者。真宗大谷派僧侶。
- 本願
- 全ての生きとし生けるものを救いたいと発された阿弥陀仏の願い
清沢 満之(きよざわ まんし)
西本 祐攝(ゆうせつ)氏
大谷大学准教授
『今日のことば(2020年)』(東本願寺出版)より
教え 2024 09


お寺に伝わる笑い話。豆腐好きの和尚さんは、毎日小僧さんに豆腐を買いにいかせました。途中に荒物屋さんがあって、ご主人が毎日小僧さんに声をかけるのです。「やぁ小僧さんこんにちは、どちらへ」「はい、和尚さんのお使いでお豆腐を買いに行きます」「そうですか。それはお気をつけて」という具合です。
だんだん嫌になってきた小僧さんは困って和尚さんに相談しました。「あの荒物屋さんのおじさんが、わかっているのに毎日行先を聞くのです。黙らせる方法はありませんか」「そうかそれなら、私は仏道修行の身、この道を歩んで浄土へ参りますと言ってみなさい」「それはいい」と言って、勇んで出かけました。
いつものように荒物屋のおじさんが声をかけます。「小僧さんどちらへ」。待ってましたと小僧さんは「道を歩んで浄土へ参ります」と言いました。おじさんはびっくりして目を丸くしました。そして尋ねたのです。「浄土へは何の為に行くのですか」。今度は小僧さんがびっくり、それは聞いていません。下を向いてもじもじしながら小さな声で答えました。「浄土へ豆腐を買いに参ります」。
パキスタンの天親(てんじん ※)と中国の曇鸞(どんらん ※)は、「浄土」とは五つの門だと表しました。浄土の世界が始まる近門(ごんもん)、たくさんの人と出会える大会衆門(だいえしゅもん)、浄土の屋敷の門である宅門(たくもん)、さらに浄土の部屋の入り口である屋門(おくもん)、そしてそれに続く門が人間の迷いの現実に還る園林遊戯地門(おんりんゆげじもん)です。
そうです。浄土は現実を離れて往きっぱなしになって座り込む世界ではないのです。浄土は、仏様の目覚めの教えを受けて、人間の迷いの世界から一歩も身を引かず、迷いを問題にして生きる私を支える世界なのです。
- 天親(400~480年頃)・曇鸞(476~542)
- …ともに親鸞の思想に影響を与えた七人の高僧に数えられる。
四衢 亮(よつつじ あきら)氏
真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)
仏教語 2024 09


暑さが過ぎ去り台風も過ぎ去り稲穂が実る時期となりました。
稲穂が実る姿を見ると「実るほど頭(こうべ)を垂れる稲穂かな」という言葉を思い出します。
実れば実るほど、まるで有難うとお辞儀をするかのように稲穂が垂れ下がる様子を詠んだ句です。あらためて、普段の自分の姿が頭を垂れる稲穂の姿とかけ離れていると実感します。
どうしても、自分がこれまでした経験や価値観を正しいと思い込み、頭が下がらずいつの間にか傲慢(ごうまん)になっている私がいます。
親鸞聖人はご自身のことを「愚禿(ぐとく)」と名乗っておられます。
『愚禿鈔(ぐとくしょう ※)』には「愚禿が心は、内は愚にして外は賢なり」と書かれており、「私の心は外見では賢く振舞っているが、その中身は煩悩(ぼんのう)にまみれ、愚かである」という意味です。
多くの研鑽(けんさん)を積まれてこられた親鸞聖人が「愚禿」と名乗られたお姿こそ「実るほど頭が下がる稲穂かな」の句に当てはまるのではと思います。
- 愚禿鈔
- 親鸞の著作。浄土教の先徳の教えを通して、親鸞自身の信心の立場を明らかにした論書。
加藤 恵氏
真宗大谷派 光林寺住職(大分県)
九州教区ホームページ「今月の言葉」より
法話 2024 09


「聞けば気の毒、見れば目の毒」
東北の震災のとき、「てんでんこ」ということばが耳を引いた。「てんでんこ」、津波が来たときには他人にはかまわないでとにかく逃げるということ。これは、何をおいても一刻も速く、ということで、「我先に」という意味ではない。ひとは仲間を捨て置くことはできず、手を貸そうとしてつい逃げるのが遅れるから、みなが助かるためにはそれぞれに一目散、高台へ向かえ、という意味だという。
「聞けば気の毒、見れば目の毒」も、たしかに、知らずにいればすむことを、なまじ聞いたり見たりしたために、心がひどく揺らいてしまうことを言っているのだが、これを裏返せば、それほどにひとは他人の苦しみ、悲しみに心をなびかせずにいられないということなのだろう。ひとは他人の苦しみに苦しみ、悲しみに悲しむのだ。
英語で「同情」や「共感」のことを、シンパシーとかコンパッションという。これも語源をさかのぼれば「苦しみを共にする」という謂(いい)である。
だから、その苦しみ、悲しみを取り除いてあげられないとき、苦しみや悲しみはさらにきびしいものとなる。最後の最後、目をつむり、見捨てるほかなくなる。
「猿を聞人(きくひと) 捨子に秋の 風いかに」
猿の声は悲しいもので聞くひとの胸を締めつけると昔から言われてきたが、秋風のなかで泣く捨子の声は、それとは比べものにならないくらいに哀れに聞こえないか、と芭蕉は心のなかで詠んだ。そして袂(たもと)から一時(いっとき)の食い物を取り出し、子のもとに置いて通り過ぎた。そのときこの子を捨てた親の思いにまで心をなびかせ、いっそう深く哀れんだことだろう。これもまた「てんでんこ」の一つのかたちである。
かつて金子郁容(いくよう)は、現代のボランティアを、あえてじぶんを傷つきやすい場所に身を置くことだと言った。「聞けば気の毒、見れば目の毒」とわかっていて、それでも被災地に行き、聞こう、見ようとしたのが、震災ボランティアだった。苦境のなかにあるひとの話を聞きながら、しのびない、返すことばがないという思いに身もだえしながら、きっと思い知ったことだろう。聞き流す、あるいは聞かなかったことにするという心ばせをどこかで持たねば、最後まできくことはできない、と。
鷲田 清一氏
哲学者
『シリーズ人間の問い②』
(東本願寺真宗会館)より
著名人 2024 09