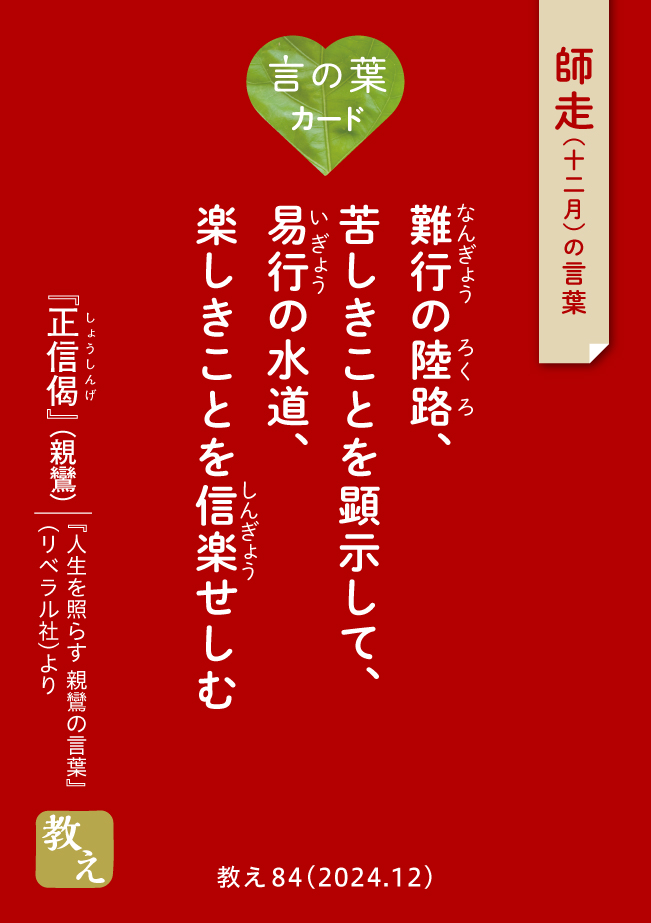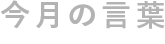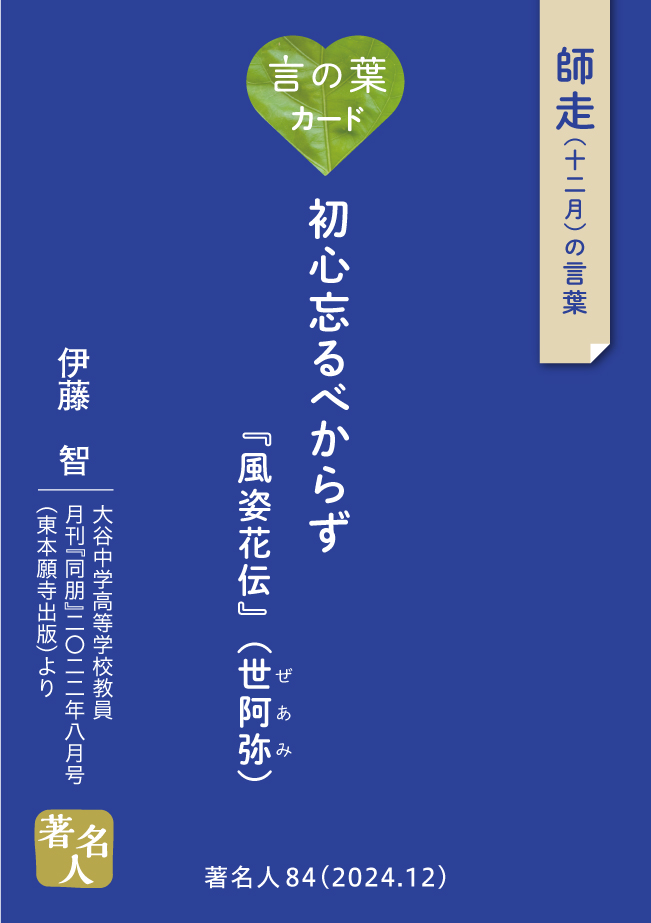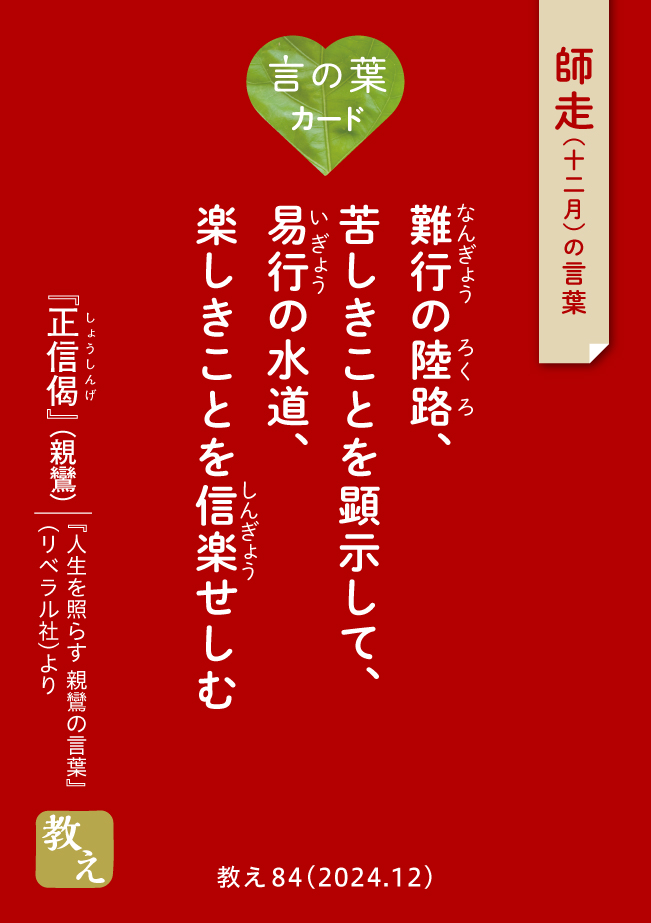
この言葉は、インドの龍樹(りゅうじゅ ※)という方が説いた難行(なんぎょう)と易行(いぎょう)の道について、親鸞が『正信偈(しょうしんげ ※)』で讃えている部分の一節です。
仏教でも山登りなどと同じように、目的地(さとりの世界)まで行くにはさまざまな方法があります。険しい谷や山を歩いて進んでいく方法や波一つとない穏やかな水路を進む方法など…。
生きることにはさまざまな苦しみや困難が立ちはだかります。自分の力では何ともならないこともあります。その時、水の流れに身を任せ、「今、ここ」を生きていくこと、それが水路を行くということなのかもしれません。
- 龍樹
- 二世紀頃の南インドの僧。大乗仏教の確立に大きな影響を与えた。
- 正信偈
- 正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)。真宗門徒が朝夕お勤めする親鸞が書き記した漢文の詩。
『正信偈』(親鸞)
『人生を照らす 親鸞の言葉』(リベラル社)より
教え 2024 12


「おそくかえっているあいだに、ぼくをさがしてた」。これは「自分が大事にされた体験」を尋ねたアンケートに答えてくれた一人の子どもの声です。夕闇がせまり心細くなって家に急ぐ中、探している両親に出会ったのでしょう。
「遅くなったね」と声をかけ抱いてもらい、「自分を心配し探して回ってくれる」親の温かさを感じ、大事にされていることを知ったのです。
「名」という字は、夕と口が合わさった文字です。夕闇の中でその姿がはっきりしない中、「ここにいるよ」と声となって名のって存在を知らせることを意味します。「おーい、お母さんよ」「お父さんだよ」と声をかけてくれたように。
「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」は、「名号(みょうごう)」と言われるように、名前となった仏様です。なぜ仏様が名前になったのでしょうか。
「自殺しようとして、できなくて、帰ってきたとき、友だちが泣いてくれたこと」。これは先ほどのアンケートに答えてくれた一人のおとなの言葉です。死ななかったことを何より安堵して、死にたいほどの辛さを一緒に泣いてくれる友だち。悲しみ分かち合ってくれる友の存在が、私たちが生きる支えです。
私たち人の世は力ずくの世界だと仏様は言われます。力には力で対抗しようと争い、争いは怒りをよび、恨みになって互いが滅ぶまで争います。
その争いを繰り返す人間の歴史を悲しみ、その愚かさに目を覚まして一緒に課題としようと願った仏様が、闇の中で自分たちを見失う私たちに、呼びかける名前となったのです。名前に呼ばれて目を覚ました人は、その願いを支えに、その名前「南無阿弥陀仏」を声に出して、歩む人になるのです。
四衢 亮(よつつじ あきら)氏
真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)
仏教語 2024 12


-

『源氏物語』の「宇治十帖(じゅうじょう)」に「薫の君(かおるのきみ)」という人物が登場します。光源氏の息子という設定ですが、そのしぐさにえも言われぬ芳香を帯びていたことからそのように呼ばれるようになりました。
紫式部の身近にあった香りとはどのようなものだったのでしょう。伽羅(きゃら)か沈香(じんこう)か。時代は移り、親鸞聖人の修行の場に漂っていた香りはいかなるものだったか。仏教の言葉に「薫習(くんじゅう)」というのがあります。香りが物にその香を移していつまでも残るように、自らの行為が心に習慣となって残ることを意味します。日ごろの行いや思いがいつの間にか積み重なって「私」を作っているというのです。
真宗大谷派の学僧である安田理深先生が「顔は履歴書です」と言われました。日ごろの私の思うこと行うことが、いつの間にか私の「顔」になっているのです。
茶道の稽古をしていて、この「薫習」を思い知らされることがありました。茶碗を持って茶杓(ちゃしゃく)を持って、さて次にどの所作をすればよいのかを忘れてしまった時に出てきたのは、日ごろ身についてしまっているかなりいい加減な所作でした。
「いつもは違うのよ、今回はたまたま」とその場をとりつくろったとしても、ふと気を抜いた時に出てくるのはまぎれもなく「日ごろの私」なのです。
また、このようなことを聞いたことがあります。「歌舞伎役者の家に生まれた子どもは3歳になったあたりから稽古を始めます。せりふを体で覚えるんです。そうするとどんな大舞台でも、たとえあがってしまってもせりふはちゃんと出てくるんです」。
歌舞伎の世襲という話題の時にたまたま出た話ですが、こうしてせりふを積み重ねている役者さんもいることに驚きました。
「薫習」ということをこれまで多くの人がいろいろな場所で教えてくれていたにもかかわらず、それほど気にもとめずにきてしまったのだなあ、という後悔が今の私の心境です。
親鸞の「浄土和讃(じょうどわさん ※)」の中に
染香人(ぜんこうにん)のその身には
香気(こうけ)あるがごとくなり
これをすなわちなづけてぞ
香光荘厳(こうこうしょうごん)ともうすなる
と、匂い立つような和讃があります。香に染まる人って、どんな人でしょう。
先ほどの『源氏物語』の「薫の君」のように、その雰囲気の中にえもいわれぬ香りを醸(かも)し出す人でしょうか。
「顔は履歴書」。年を取って何ともいえずいい表情を見せてくださる人がいます。それまで経験されたことが深く積み重ねられているような表情。それは世間でいう有名な方とは限りません、身近にいるじいちゃんばあちゃんの中にもいます。
生きることに悪戦苦闘しながらも現実から足を離さず、そこにしっかりと目を向ける。そのことの積み重ねがやがて顔に、しぐさに、「香」を帯びていくのかもしれません。香りは余韻でもあります。
出会った後に、深い余韻がほのかに残る。私もかくありたいと思っています。
- 和讃
- 親鸞が人々に親しみやすくつくった詩
小丸 洋子氏
真宗大谷派 正西寺(福島県)
月刊『同朋』2022年8月号
(東本願寺出版)より
法話 2024 12

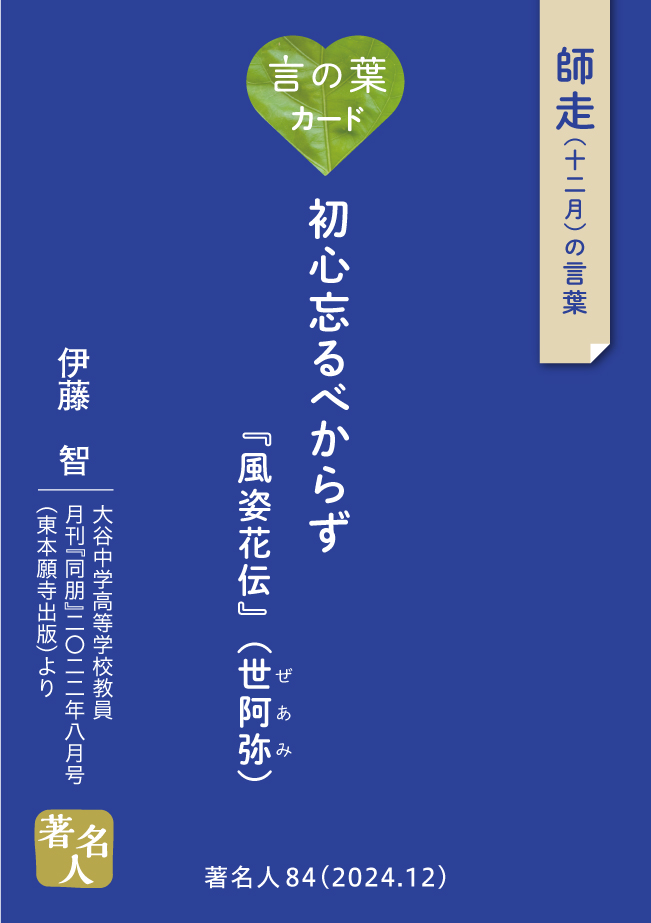
誰もが一度は耳にしたことのあるこの言葉。これは室町時代に能を大成した世阿弥(ぜあみ)の言葉です。一般的には、初めの志(こころざし)を忘れてはならないという意味に理解されていますが、実はもう少し複雑な意味を含んでいます。世阿弥が言った初心とは、「若い時の気持ちに返って」という意味に限りません。人生の中にはいくつもの初心があって、老後には老後の初心があるとされます。世阿弥は決して「心も体も若くあれ」と言ったのではありません。体力を保つことだけでなく、歳を重ね、老いに向かっていく人生の中で、いかにして花を咲かせるか。思い通りにならないことが増えていく中でも、その時にしかできない花の咲かせ方があると、この言葉は教えてくれています。
老いに限らず、病いや死、さまざまな側面において、私たちの人生は思い通りにならないことで溢れています。「なんで私なんだ…」と思いたくなることも生きていればたくさんあります。けれど、上手くいかない時の自分も、思い通りにいかない時の自分も、そのままに受け止めながら私の花を咲かせていきたいです。
伊藤 智氏
大谷中学高等学校教員
月刊『同朋』2022年8月号
(東本願寺出版)より
著名人 2024 12