
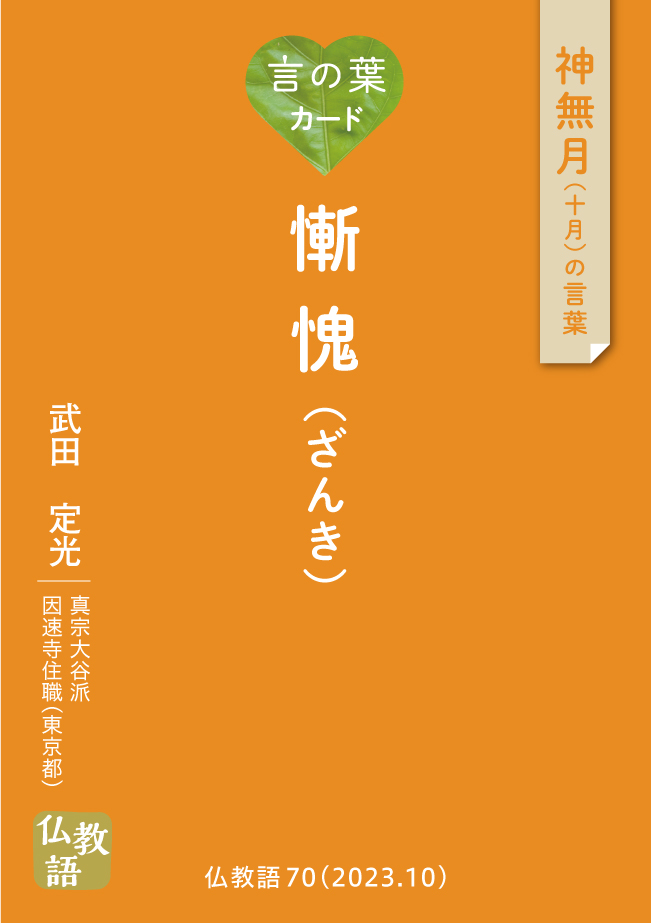
「慚愧(ざんき)」は「自らおかした悪行を恥じて厭(いと)い恐れること。慚は自らをかえりみて恥ずかしく思うこと。愧は他人に対して恥ずかしく思うこと」(『岩波仏教辞典』)です。ひと昔前は、「世間様に顔向けできない」などという言葉があったように、「世間」という基準が倫理を支えていました。しかし、現代では「世間」という意識も薄くなり、倫理基準が曖昧になりました。そもそも、倫理の基本は何かと言えば、「自分がしてほしくないことを、人にしてはいけない」ということに尽きるようです。
さて、「慚愧」で思い起こされるのは、『涅槃経(ねはんぎょう)』に出てくる阿闍世王(あじゃせおう)のお話です。父王を殺した罪に怯え、悩んでいた阿闍世に対して、友人である耆婆(ぎば)が、次のように言います。「「慙」は人に羞(は)ず、「愧」は天に羞ず。これを「慙愧」と名づく。「無慙愧(むざんき)」は名づけて「人」とせず、名づけて「畜生(ちくしょう)」とす。」(『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』信巻)と。
「慚愧」は自分に対して、そして社会に対して恥ずかしいと思うことであり、もしこのこころがなければ、それは人間以下なのだと。耆婆は罪に怯える阿闍世を、「あなたは人間である」と褒め、このこころがある故に苦悩しているのだと共感します。「慚愧」のこころが、人間に踏みとどまれる最後の砦(とりで)だと言うのでしょう。しかし、このこころがあるために阿闍世は苦しむのです。確かに「慚愧」は、人間であることの証明ですが、このこころのままでは救いには至れません。
阿闍世は耆婆に導かれて釈尊(しゃくそん/お釈迦さま)に出会います。そして、「慚愧」から「懺悔(さんげ)」へと深まっていくのです。「慚愧」とは、自分がした過去の間違いを悔い改めようとするこころですが、それは、罪を犯した自己を裁き、罪なき者になろうとするこころでもあるのです。『歎異抄(たんにしょう)』で言えば、それは「自力のこころ」です。できれば犯した罪を消し、善なるものとなって救われようとする「善人根性」です。釈尊に出会った阿闍世は、やがて地獄に行っても後悔しないという「無根の信」を得ていきます。これが「慚愧」から「懺悔」への翻身(ほんしん)です。もはや自分の犯した罪を、帳消しにしようとする思いが破られ、罪と一つに同化したのです。それは、この世のすべての苦悩するものが救われたとしても、私はその一番最後に救われるものだという確信です。
武田 定光氏
真宗大谷派 因速寺住職(東京都)
仏教語 2023 10



