
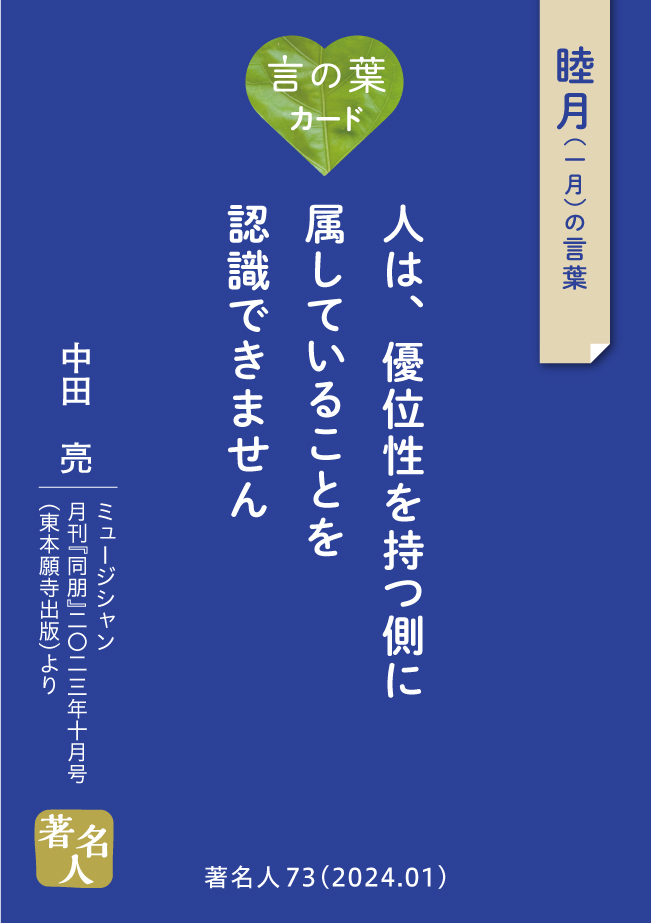
ずいぶん前ながら、こんなことがありました。僕の娘、小学4年生との話です。
「Aちゃんっていう友達が、知らないオジサンについていってん」
「えっ、知らないオジサンについてったの? それはタイヘンなことやんか!」
「公園でお婆さんが倒れてたらしい。それでAちゃん一人では助けられないから、通りかかった男の人にお願いしてん」
「ほんで?」
「そのお婆さんは大丈夫で、二人で家まで連れていった。そのあと、オジサンが、〈じつは、この番地の住所の家をさがしてるんだけど、どこか分かる?〉って訊いたらしい。〈それなら近くのはずだよ〉と言って、一緒に探してあげたんやって。それでその家はすぐ見つかった。だから何事もなかったんやけど」
「なんだ、そんなことかあ。それなら、よかったやん。〈ついて行った〉っていうわけでもないやん」
―ここからが本題です。
「え、なに言うてんの、大問題やん。絶対ついていったらアカンやん?」
「そう? 僕なら同じことするかも。知らない土地で〈お嬢ちゃん、駅にいくのはどっちか教えてくれる?〉とか、公園でヒマつぶしに〈おにいちゃん、カッコいいオモチャ持ってるねえ〉とか」
「えっ! それは絶対にアカン。完全にアウトや。それはフシンシャや」
驚いてしばらく考え込んでしまいました。「そんな馬鹿な話があるか、僕は不審者じゃないぞ、子どもは世の宝だ、近所の子どもと挨拶したっていいじゃないか」と。
でもそれは許されないことです。
自分が「男性」「おじさん」という抑圧者のグループに属しており、僕ではない他のオジサンが子どもにいたずらをするような事件が実際に起きているので、知らない人と口をきいてはいけないと世の子ども達は教えられているのであり、それを大人は常識として知っておかねばならず、したがって僕は子どもにみだりに話しかけることはできないのです。
きっと、差別を無くすとはこのようなことではないかと思うのです。
人は、優位性をもつ側に属していることを認識できません。男と女とか、先輩と後輩とか、上司と部下とか、医者と患者とか、お金持ちとそうでない人とか、教師と生徒とか、大家さんと借主とか、大企業と消費者とか、行政と市民とか。障害のない人とある人、自分の身体に文句のない人、そうでもない人。
視界をひっくりかえして弱い者の側からの視点にたつことができれば簡単にわかることなのに、思わず、「オレはちがうぞ、オレはいじめてないぞ」と頭にめぐらせてしまう。
本当に「オレはちがう」のか、それが問題です。
強い側にいると、いくら耳にしても目にしても信じることができず、血や涙がそこらじゅうに流れていて、世にあふれているのに、それでも気づくことがありません。
中田 亮氏
ミュージシャン
月刊『同朋』2023年10月号(東本願寺出版)より
著名人 2024 01



