
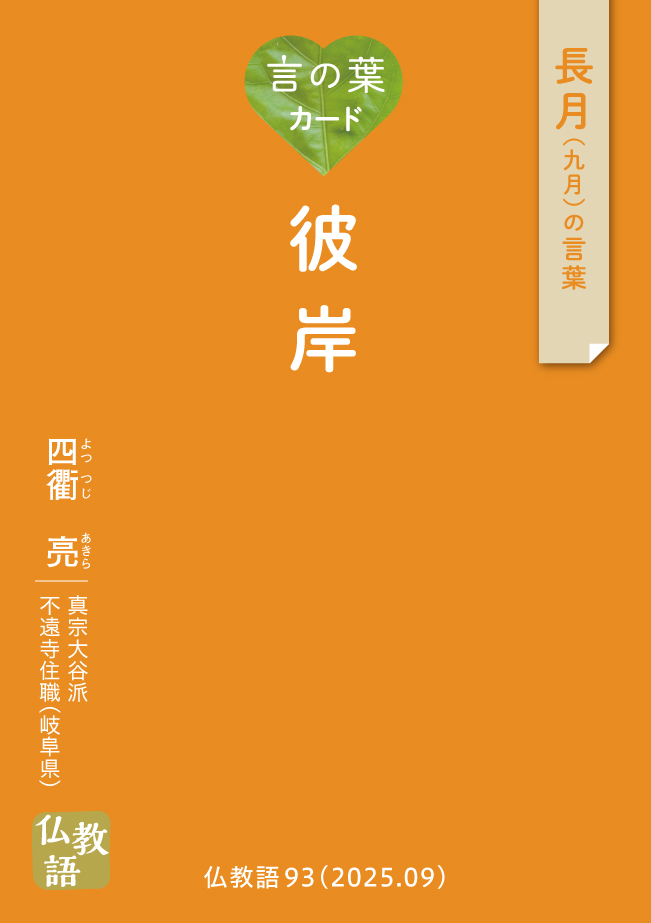
春分の日と秋分の日を中日として前後三日間、計七日間行われる彼岸の法会(ほうえ)は、日本独特の仏事で、江戸時代に年中行事化したそうです。
インドの言葉のパーラミターという言葉が、「到彼岸(とうひがん)」と訳されます。迷いのこちらの岸(此岸/しがん)から迷いの海を渡り、目覚めの彼(か)の岸に到るという意味です。これが仏教が課題としたことだと言っていいでしょう。
親鸞聖人も、阿弥陀仏(あみだぶつ)の本願(※)こそが、渡りがたい迷いの海をよく渡す大きな船なのだと言われます。
それなら、「彼の岸」ってどこにあるのだろう。渡るといっても、いつ渡るのかということが疑問です。そして死んだ向こうに彼の岸があって、死んでから渡るということなら、今ここにいる私には、とりあえず関係ない、ということになります。
しかし大切なことは、「渡り難い迷いの海」に今沈みかけているあなたが居る、ということです。そのことを私たちに目を覚まして欲しいと願う世界が「彼の岸」です。
ですから「彼の岸」は遠く離れた彼方にあるのでも、死んだ向こうにあるのでもなく、今ここにある私の事実を知らせてはたらく世界です。
そのはたらきによって、今だけでなく、歴史が始まって以来これまで、迷いの海に沈んでは浮かび、また沈んでは流されてきたと、今知るのです。
- 阿弥陀仏の本願
- 全ての生きとし生けるものを救いたいと発された阿弥陀仏の願い
四衢 亮(よつつじ あきら)氏
真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)
仏教語 2025 09



