
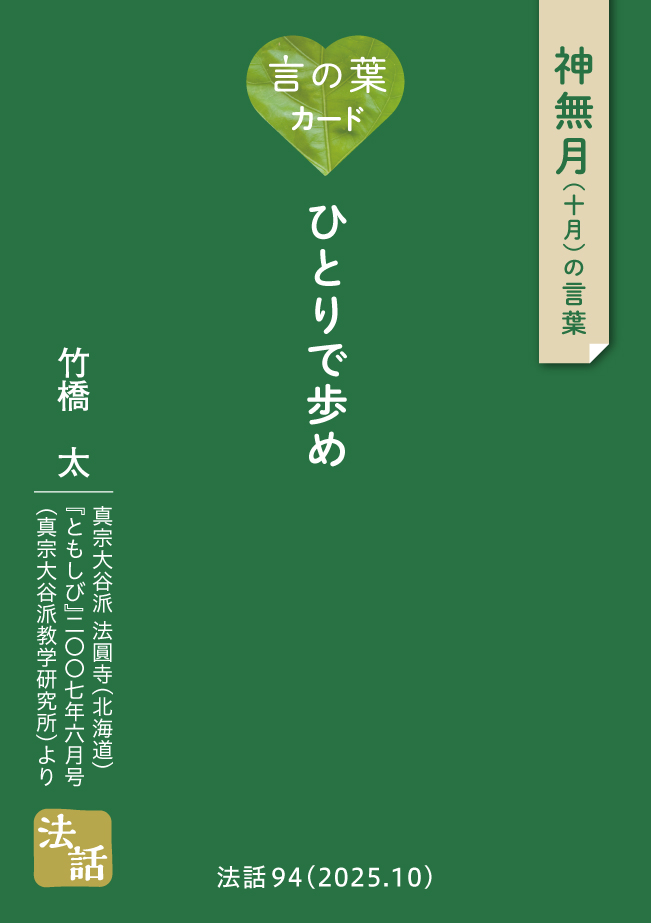
お釈迦(しゃか)さまがなくなってから、教団は長老の大迦葉(だいかしょう)と阿難(あなん)などによって受け継がれたようです。お釈迦さまの言葉を記憶して、それを「如是我聞(にょぜがもん ※)」と語りはじめたのが、その阿難です。
阿難は釈尊(しゃくそん/お釈迦さま)のいとこで提婆達多(だいばだった)の兄弟です。記録によって兄とも弟とも言われています。伝説では釈尊三十五歳の成道(じょうどう―おさとりをひらかれたこと)のときに生まれたので、それを喜びとしてアーナンダ=歓喜という名前がつけられたとも言われています。
お釈迦さまが成道後、生まれ故郷のカピラヴァストゥにはじめて説法に行かれたときに、一族の者がたくさん弟子になったようです。阿難もそのひとりのようです。その時に弟子になったとすれば、阿難はもう少し早くに生まれていたと思います。しかしその時から阿難は常随昵近(じょうずいじっきん―常におそばにつかえること)の弟子としてお釈迦さまと離れることはありませんでした。お釈迦さまがなくなったのは八十歳のことですから、阿難は四十数年の間おつかえしたことになります。また経典を暗誦(あんしょう)したのが阿難であるならば、たくさんの説法を聞いて、よく仏法を理解していたと考えられます。ところが、今残されている経典を見る限り、阿難はそのように描かれてはいないのです。
釈尊が最後の旅でペールヴァ村で病に倒れますが、いったんは回復します。それに安心した阿難に向かって、こう言われました。
阿難よ、比丘(びく)たちはわたしに何を期待するのだ。私は内外の隔てなしに法を説いた。阿難よ、如来(わたし)の法には、師拳(しけん―師だけが特別に持っている秘密の真理)はない。―中略― それ故に、アーナンダよ、この世で自らを燈(ともしび ※)とし、自らを依り所として、他人を依り所とせず、法を燈とし、法を依り所として、他のものを依り所とせずにあれ。(パーリ『大般涅槃経―だいはつねはんぎょう』)。
何ももう教えることはないのだ、ひとりで歩め、こうお釈迦さまは阿難に言われるのです。
そばにいるから聞こえないことや、見えないことがあるのかもしれません。阿難は、どうしてもお釈迦さまに頼ってしまって、自ら考えることを止めてしまっています。しかし「頼る」ということは、「あの人は素晴らしい」という自分の評価によっておこるものです。それは実は自分の思いです。お釈迦さまを特別なものとしている自分自身を信じている、そういう問題が阿難にはあるのです。
阿難とはいったい誰のことなのでしょうか。私たちも親鸞聖人を宗祖と言っていますが、そこに同じ問題はないでしょうか。そのことが見えてきたとき、はじめて師が言葉として、「如是我聞」の内容として私の中に生まれるのではないでしょうか。
- 如是我聞
- 「私はこのようにお釈迦さまの説法を聞きました」という信仰告白
- 燈
- 本来は「州(=中州)」、「島」が正しい訳とされていますが、漢訳の伝統的な表現に倣って「燈」としています。
竹橋 太氏
真宗大谷派 法圓寺副住職(北海道)
『ともしび』2007年6月号
(真宗大谷派教学研究所)より
法話 2025 10



