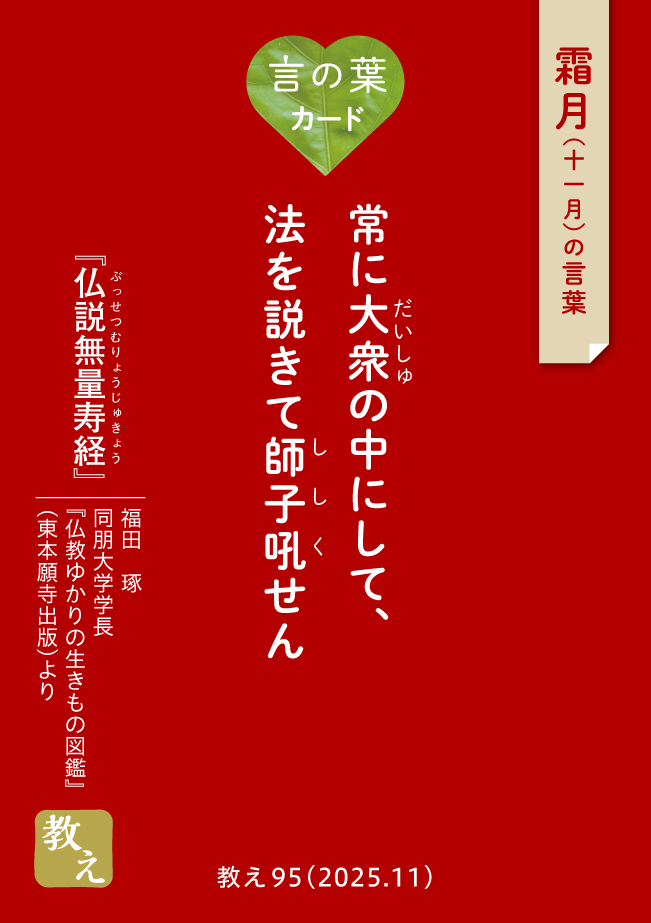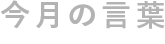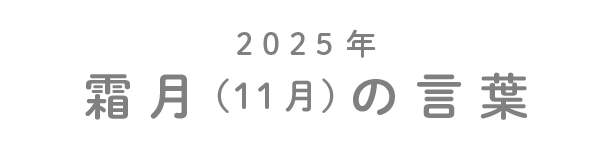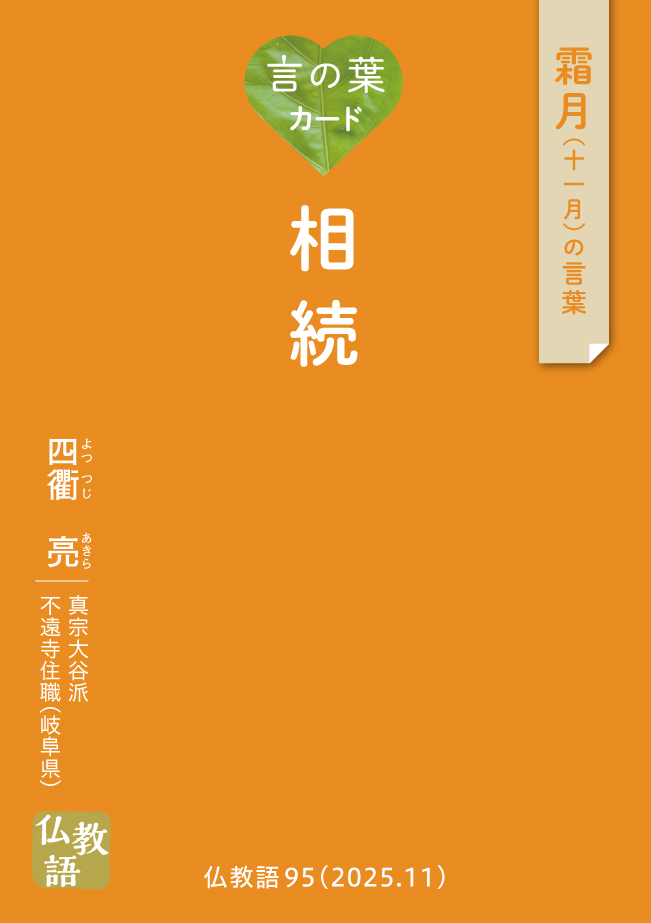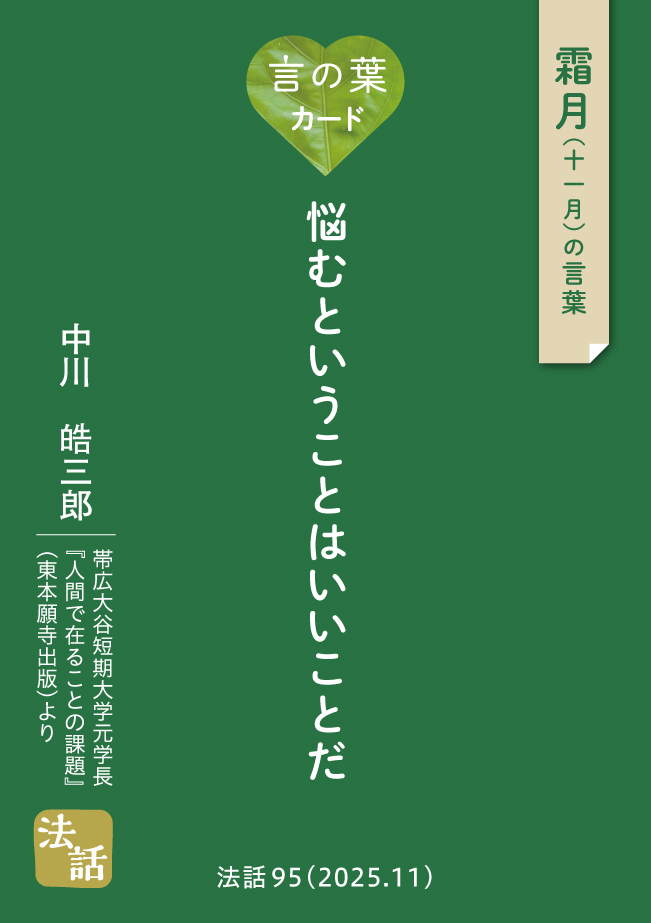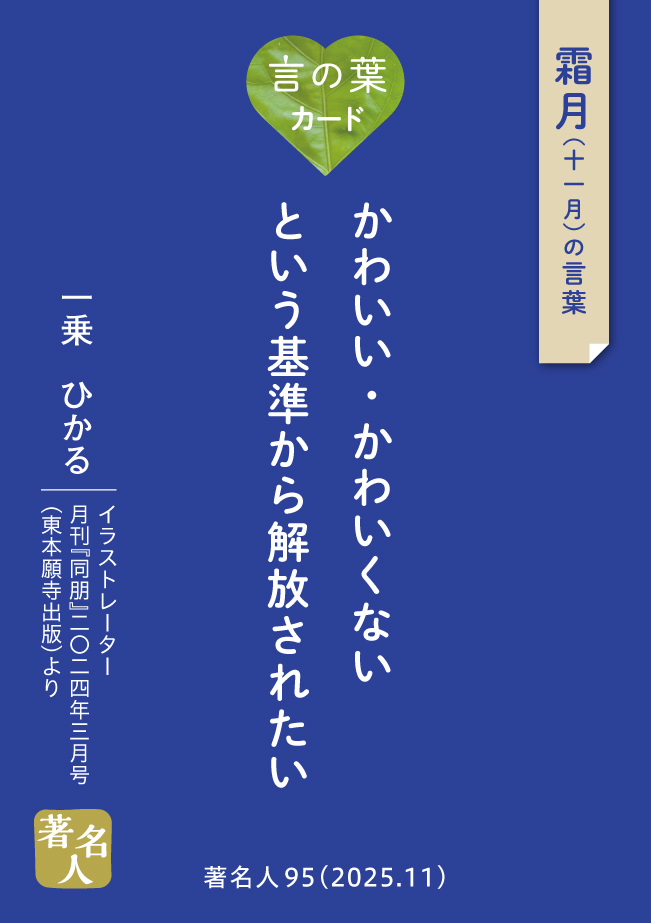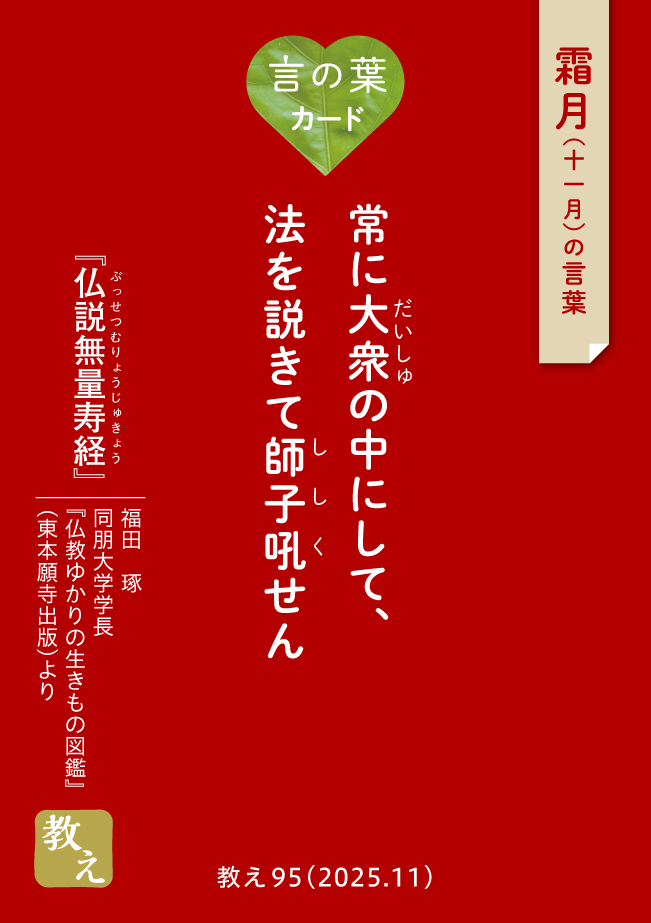
百獣の王ライオンが吼(ほ)えたときのように、ひとたび仏が説法(せっぽう)すれば、誰もがその威厳と力強さに圧倒され、畏怖(いふ)の念をもってひれ伏します。『無量寿経(むりょうじゅきょう)』『法華経(ほけきょう)』『華厳経(けごんぎょう)』など、あらゆる経典(きょうてん)で、仏の説法は「師子吼(ししく)」と呼ばれます。
インドの国章は、台座の上で四方を向いて立つ四頭のライオンを図案化したもので、「アショーカの獅子柱頭(ししちゅうとう)」と呼ばれる彫刻が元になっています。アショーカ王は紀元前三世紀にインド統一を成し遂げ、後に篤(あつ)く仏教を信仰したことで知られており、この彫刻は、釈尊(しゃくそん)が初めて説法を行った聖地サールナートより出土しています―。
生息地の西北インドから遠く離れた東アジアで、「師子」はほとんど架空の生き物でした。絵師や彫刻家たちは見たこともないその姿を、想像力を駆使して描きました。そして中国では皇帝を守護する霊獣となり、日本では神社や寺院の境内に(しばしば、これもまた空想上の獣である狛犬(こまいぬ)と一対で)配置されました。
京都の東本願寺でも、阿弥陀堂(あみだどう)の屋根や御影堂広縁(ごえいどうひろえん)、御影堂門など、境内各所に日本的な意匠の獅子が見えます。しかし阿弥陀堂門の木鼻(きばな)(頭貫(かしらぬき)・肘木(ひじき)・虹梁(こうりょう)などの端が柱から突出した部分)の獅子だけは、珍しく実際のライオンに近い造形です。この門は1909年(明治42年)に起工しており、その数年前に京都市動物園にやって来た本物のライオンを参照できたようです。冒頭に紹介したアショーカ獅子柱頭を髣髴(ほうふつ)とさせるリアルさです。
インド国章の下にはサンスクリット(古代インドの言葉)で「真実のみが勝利する」と記され、この言葉も国章の一部とされています。仏教徒であったアショーカ王がライオンの姿で象徴させたのは王の威勢ではなく、王でさえもその前にひれ伏す、仏法(ぶっぽう)のもつ真実の力だったのです。
『仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう)』
福田 琢氏
同朋大学学長
『仏教ゆかりの生きもの図鑑』
(東本願寺出版)より
教え 2025 11

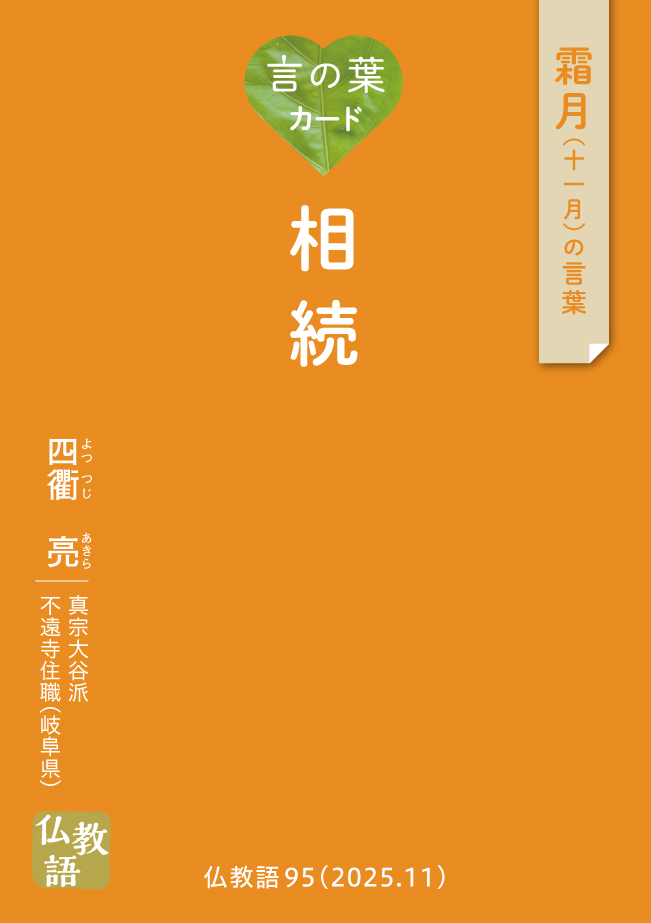
財産相続、家督相続、跡目相続など、受け継ぐという意味合いで使われる「相続」。それに税金がかけられるので相続税という言葉もあります。この「相続」は、元々仏教語です。インドのサンスクリット語で「サンタティ」または「サンターナ」という言葉の翻訳語で、人間の行為の連続性、因果の連続性を表します。
浄土真宗では、信心相続、念仏相続などの表現があります。相続は連続して持続するということですから、信心を開き、信心を問う教えが常にはたらき、念仏が継承されるということです。
それは、生活の中に時おり、念仏や真宗の教えが登場するということではありません。教えの中、念仏の中で生活が歩まれるということです。食べて寝て、起きて働いて、また食べて寝て、起きて働いてということが毎日繰り返されることが生活。特別なこともないその生活が、教えをいただき自分が問われる場所となり、念仏申す生活となることが念仏相続、信心相続ということでしょう。
ところが、身近な方が亡くなった時など、普段の生活と違った特別な時に、慌てて念仏するというようなことが実際です。また何か不都合なことが起こったり、思いを叶えたい時などに仏様を持ち出すことにもなります。
それなら、特別なことや願い事が収まれば、またケロッと忘れて、念仏も仏様もどこかへやってしまうことになります。ですから、この私たちの不相続のあり様を不断に問いはたらく教えが、私たちを捉えて相続しているのです。
四衢 亮(よつつじ あきら)氏
真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)
仏教語 2025 11

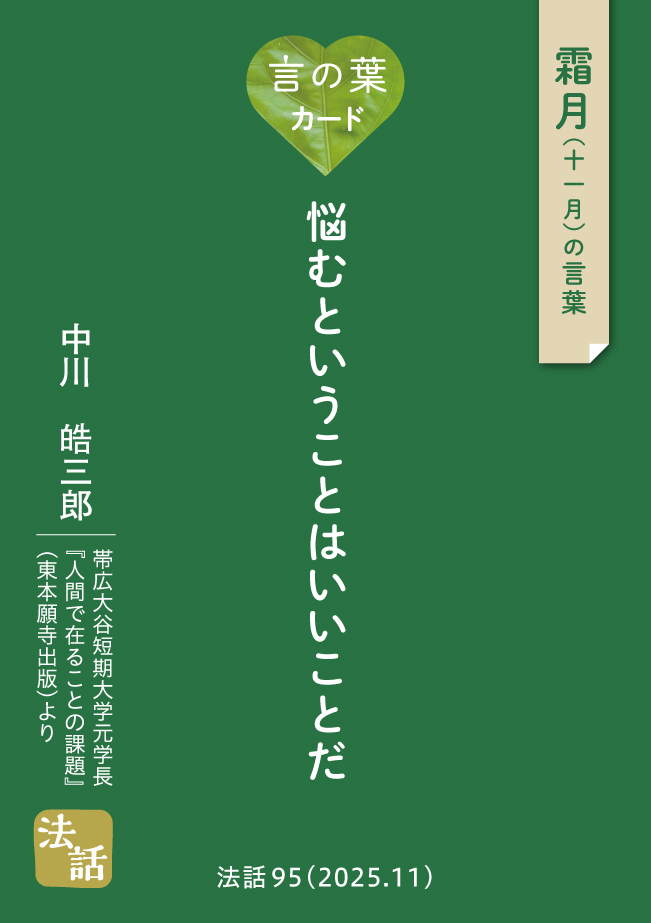
私が大学を卒業する間際、一人の先生に出会いました。その先生が私に「悩むということはいいことだ。飛び上がるときには一回沈まなければならないのだから、沈みなさい。そして立ち止まりなさい」と。そして、続いて「一緒に勉強しましょう」と言われたんですね―。
私はそのとき、この先生はいったい何を言っているのかと、訳の分からないことを言っておられるように聞こえたわけです。
つまり、現代を生きるわれわれにとって、「悩む」というようなことがいいことだとは思えないのです。悩み苦しむということはマイナスの価値であって、苦しみをいろいろな方法でなくそうとするということがあります。拝み屋さんがあったり、さまざまな相談所があったりと、そのようなかたちで、悩み、苦しみを解消し、思いどおりに生きようとするのです。
ところが、この「私」を前提にして生きる限りは、絶対に行き詰まるんだというのです。自分が、そして隣にいる人が、思いどおりにならないのです。そういう思いどおりにならない自分と、思いどおりにならない他者とが生活を共にして生きていながら、思いどおりになることが人間の生きる意味であり、人間の幸せだと考えて生きている。そのような生き方は虚なわけです。幻想なんだということです。
ですから、悩むということ、苦しむということがとても大切なのです。この「私」を前提にして生きる限りは、どんな人も行き詰まるんだと。つまり行き詰まるということが、この「私」を問いなおす、とても大きなチャンスなんだと。本当に新しい生き方を、そこに見いだすチャンスなんだということです。
親鸞聖人も、二十九歳のときに二十年もの間修行生活を送った比叡山を下りたということは、やはり行き詰まったわけです。そして、その行き詰まりをとおして、あらためて教えといいますか、法然上人(ほうねんしょうにん ※)に出遇(あ)っていったのです。そして、ご存じのように、法然上人から「ただ念仏しなさい」と教えられたということがあるのです。
- 法然上人(1133~1212)
-
日本の僧で浄土宗の開祖。親鸞の思想に影響を与えた七人の高僧のうちの一人。
中川 皓三郎氏
帯広大谷短期大学元学長
『人間で在ることの課題』
(東本願寺出版)より
法話 2025 11

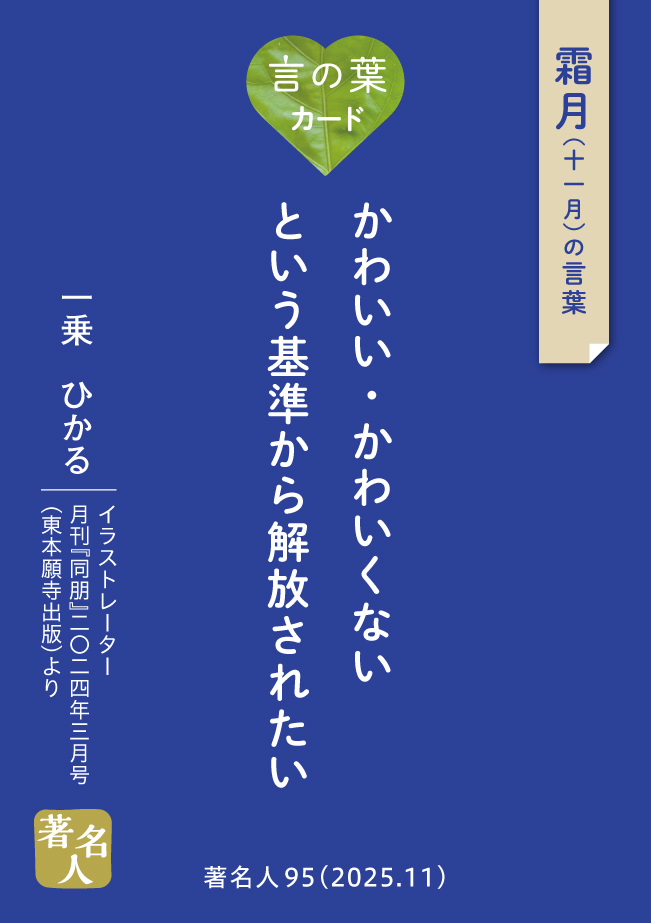
女性を描いた作品が多いですが、制作で意識されてることはありますか?
表情を描かないのは一つの特徴かなと思います。イラストの業界でも、細身でかわいい理想像的な女性が描かれることが以前は多かった。「みんなこういうのが好きだよね~」とは思いながら、少し違和感を感じていました。なので私は、かわいい・かわいくないという基準から解放されたいなと思って、表情を描かないようにしています。世の中にはいろんな人がいるのだから、いろんな人を描きたい。理想ばっかりじゃなくて、肉感的でリアルな表現も大切にしたいです。
色彩に関しても、肌や髪の色などにも自在に配色がなされ、多様な人物が描かれています。
その時の気分で使いたい色を選びます。例えばピンクを服の色に使いたいなと思ったら、肌は青色にしてみたりと、色合わせを楽しんでいます。でもこれらは、かつての広告業界ならば、敬遠されていたでしょう。この4、5年で、肌の色やジェンダーなどの多様性の大切さが少しずつ共有されてきた感があります。昔なら広告は白人女性ばかりが登場していたけれど、今は変わってきてますよね。こうした業界の変化は、見せかけのポーズと思う人もいるかもしれませんが、多くの人の目にふれる広告だからこそできることがあるはず。小さい積み重ねでも、後の世代が生きやすくなるような変化を起こす力が、広告やイラストにはあると信じています。
一乗 ひかる氏
イラストレーター
月刊『同朋』2024年3月号
(東本願寺出版)より
著名人 2025 11