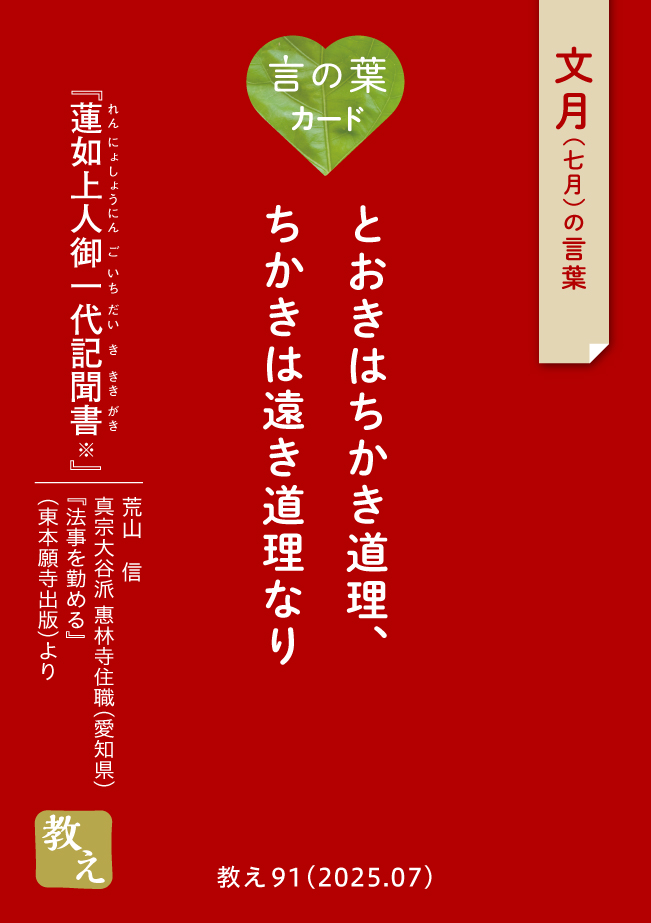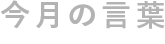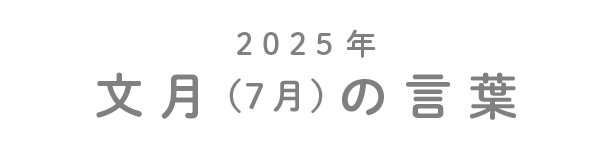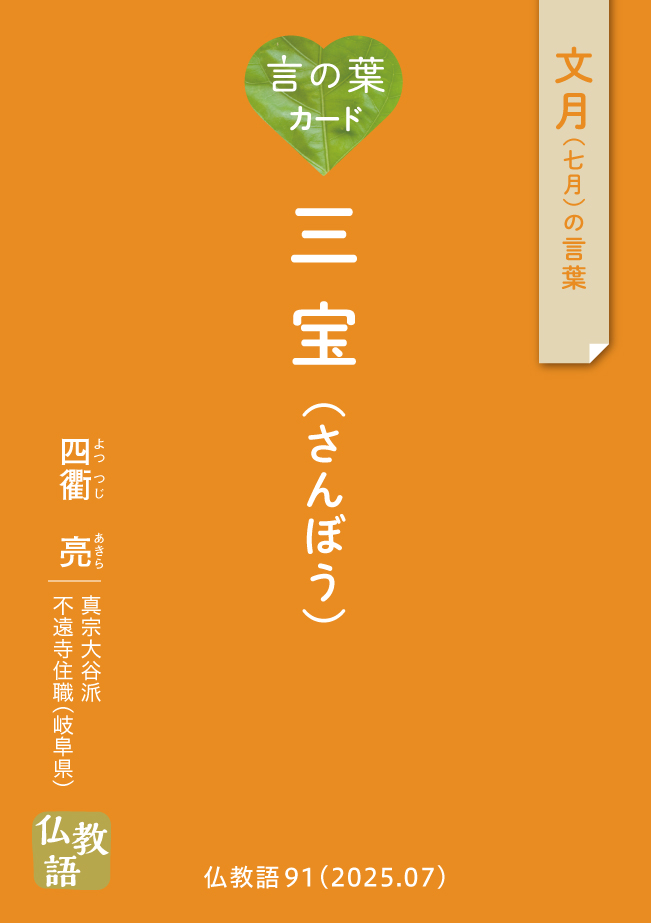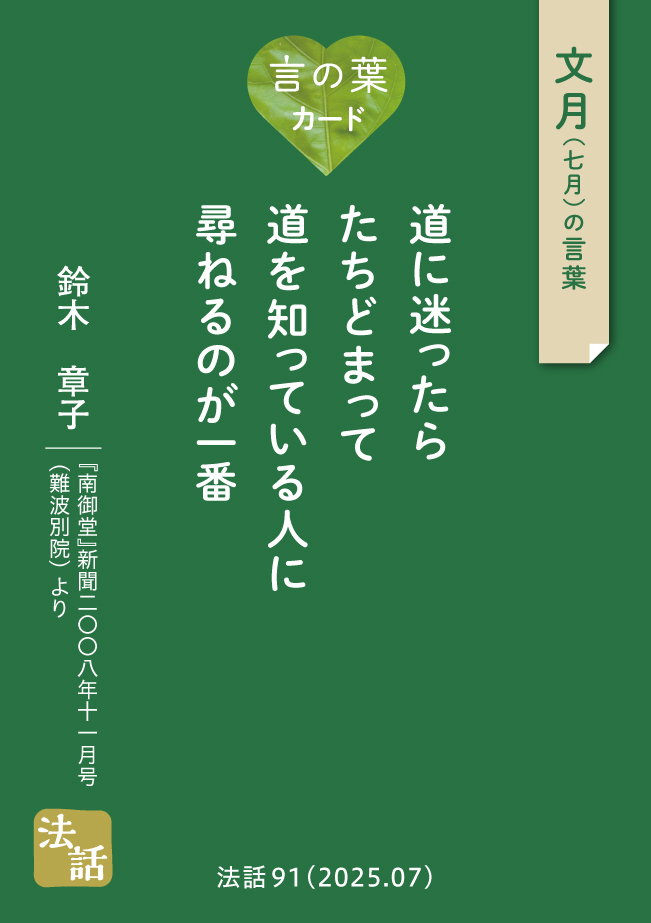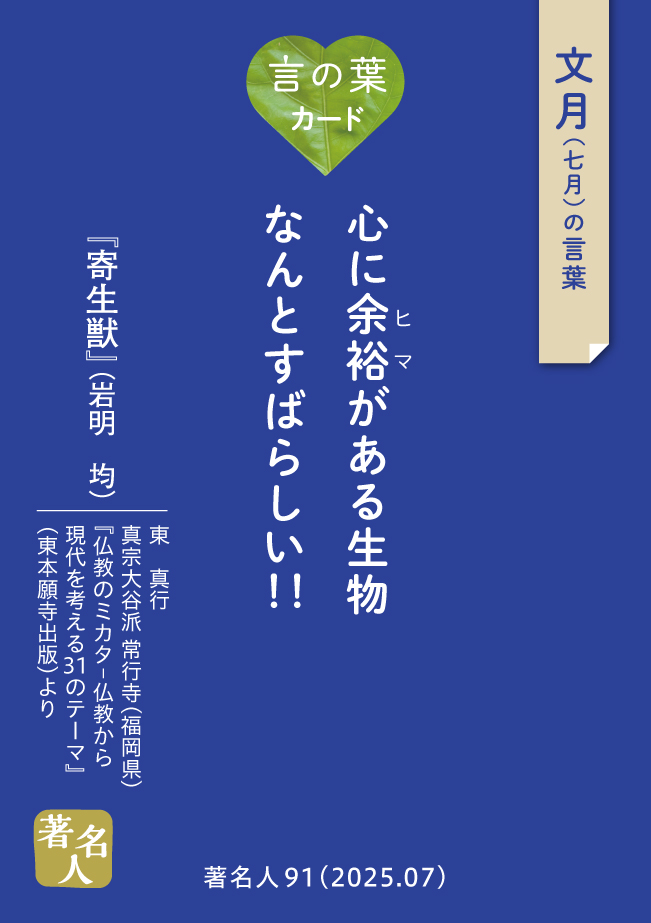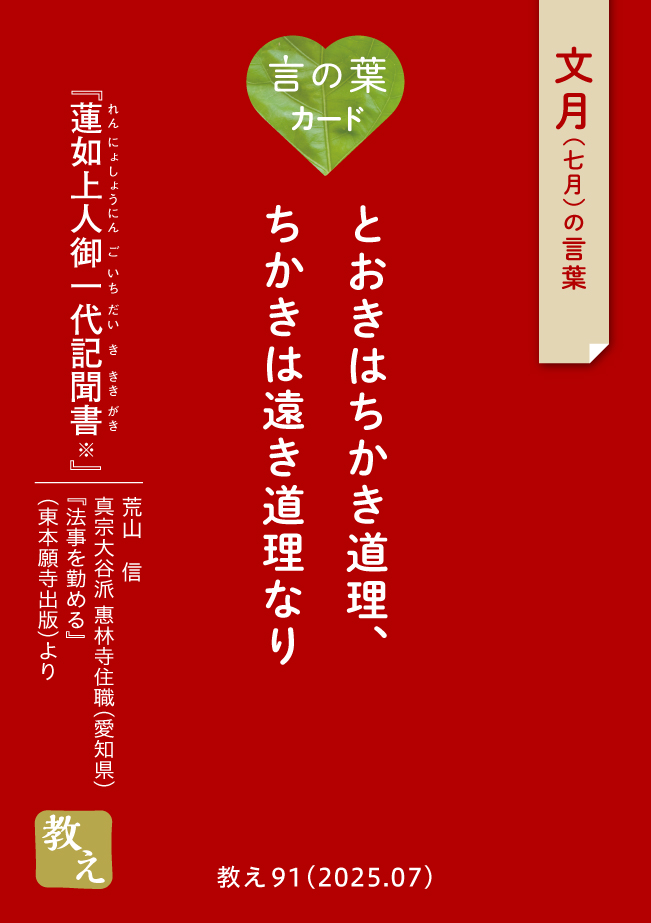
「ひとり暮らしをしてみて、はじめて親のありがたさが分かったよ」。
もう10年以上も前になりますが、県外の大学に進学した息子が帰省した際にそのような言葉を言っていたことを思い出します。
人間とは不思議なもので、そこにいる時はそこがどういう場所なのか中々気付けないということがあります。親が近くにいる時はそれが当たり前になり、親のありがたさなどすっかり忘れてしまうのです。ではそれにいつ気が付くのかと言えばそれはやはり親と離れた時なのでしょう。近くにいる時は見失い、遠ざかるといよいよはっきり見えてくるということが私たちにはあります。
本願寺八代・蓮如上人(れんにょしょうにん ※)はそのような私たちのすがたを、「とおきはちかき道理、ちかきは遠き道理なり」(『真宗聖典第二版』1051頁)と伝えてくださいます。
法事もまた同じではないでしょうか。法事とはある意味では非日常な体験です。非日常とは日常を離れた場所です。亡き人を縁とし、ご本尊の前に皆で座り、手を合わせ、お念仏を申し、お経やお聖教のお言葉に耳を傾ける。こういった場と時間は、忙(せわ)しなく過ぎていく日常の中には中々持てないのが私たちの実際ではないでしょうか。
私たちは生きていくうえで多くの問題に直面します。それは時に人間関係の問題であったり、経済的な問題であったり、健康上の問題であったり様々です。問題を解決しようと苦心しているうちにまた次の問題が生まれてくることもあるでしょう。問題を送り迎えしながら過ぎていく日々の生活から半日でも一時間でも離れ、ご本尊の前に身を置く場が法事であると私は思います。日常を離れるといってもそれは現実逃避をするということではありません。先に述べたように、離れることではじめて自分が生きている現実を見つめなおすことが出来るのです。日頃の自分の生き方をもう一度点検させてもらう大切な機会を、亡き人をとおしていただく場が法事なのです。
- 蓮如(1415~1499)
-
室町時代の浄土真宗の僧侶
『蓮如上人御一代記聞書(れんにょしょうにんごいちだいききがき)』
荒山 信氏
真宗大谷派 惠林寺住職(愛知県)
『法事を勤める』
(東本願寺出版)より
教え 2025 07

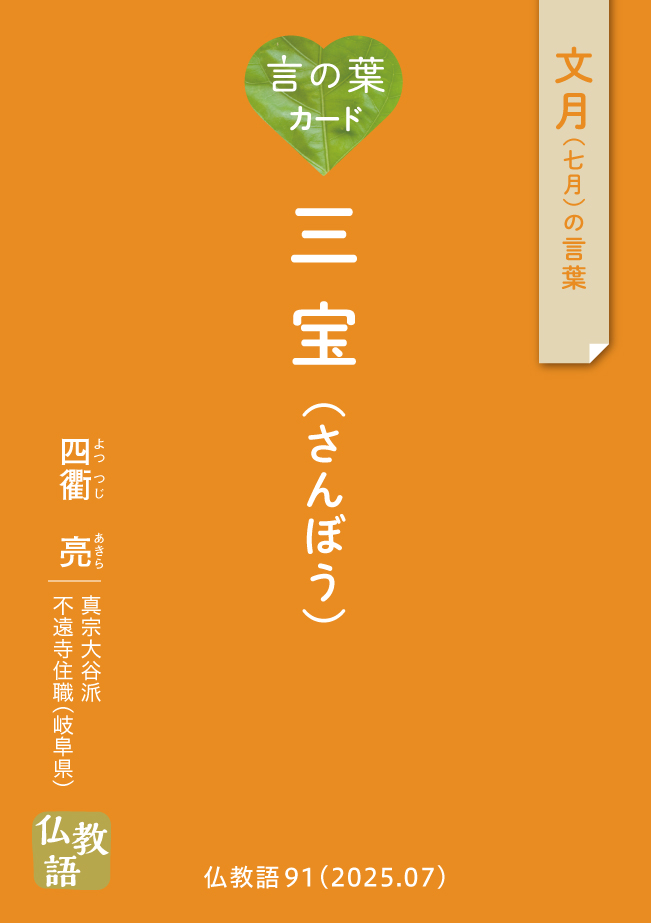
春から夏にかけて日本に来る渡り鳥のブッポウソウは、本当は「ブッポウソウ」と鳴かない、実はコノハズクが「ブッポウソウ」と鳴くのだと昭和初期になって分かったそうです。ただ鳥の鳴き声がそう聞こえるほど日本人に定着していた言葉が「仏法僧(ぶっぽうそう)」です。
この仏と法と僧を「三宝(さんぼう)」と言います。聖徳太子の十七条憲法でも、「篤(あつ)く三宝を敬え」と示されていることはご存じの方も多いと思います。
仏は、人間の迷いに目覚めた仏様です。法は、その仏様の教えを表します。僧は僧伽(サンガ)の略で、仏の教えを聞き確かめる場やなかまを表します。この仏・法・僧をあなたの人生の宝としなさいと勧められ、三宝を篤く敬えと言われるのです。
確かに仏様やその教え、さらに教えを聞くなかまも大事なものに違いないと思っても、人生の宝とするというと、ちょっとそこまではと躊躇(ちゅうちょ)する気持ちもあります。
もしそうだとすれば、私たちはそれぞれ何を人生の宝にしているでしょうか。健康が何より大事だということもあります。家族が宝だと思うこともあります。結局お金が一番だと考えることもあります。でもそれなら、病む人には人生の宝はないのでしょうか。家族が喧嘩(けんか)をすれば宝は失われるのでしょうか。お金はどれくらいあれば宝といえるのでしょうか。
実は、仏法僧の三宝とは、今私が宝と思っているもの、握りしめている宝が、本当か、人生を貫く宝か、と常に私を問うということにおいて「宝」とされるのです。
四衢 亮(よつつじ あきら)氏
真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)
仏教語 2025 07

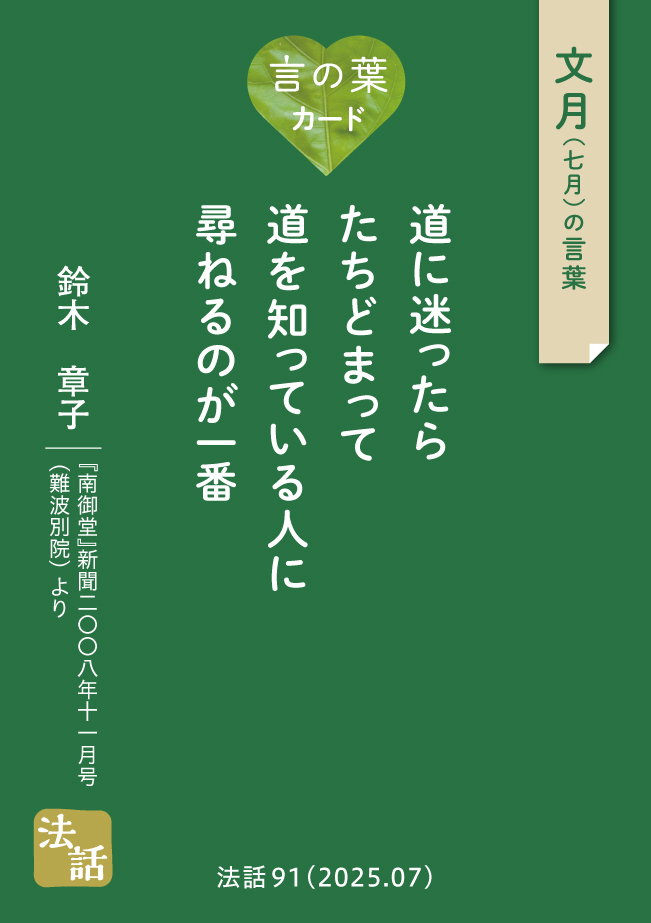
「道」という言葉には地面にある道路だけでなく、人の生き方の規範といった意味もある。
最近、友人が「今の世の中、飾りたてた偽物ばかりじゃないか。そんな中をどうやって生きていけばいいのか、わからないよな…」と呟いた。人生について悩んだり、迷ったりすることは誰にでもある。自身を振り返ると、自分で考えて答えを出してきたし、また、そうすることが社会の常識のように考えてきた。しかし、果たして本当に解決してきたのだろうか。悩むことに疲れ、都合のよい答えを出しているだけではないだろうか。本当に私はこのままでいいのだろうか。
この言葉は「そのうちにと思っていると日が暮れてしまう」と続く。どうやって生きていけばいいのかわからない今こそ、「道を知っている人」に尋ねる絶好の機会である。
鈴木 章子氏
『南御堂』新聞2008年11月号
(難波別院)より
法話 2025 07

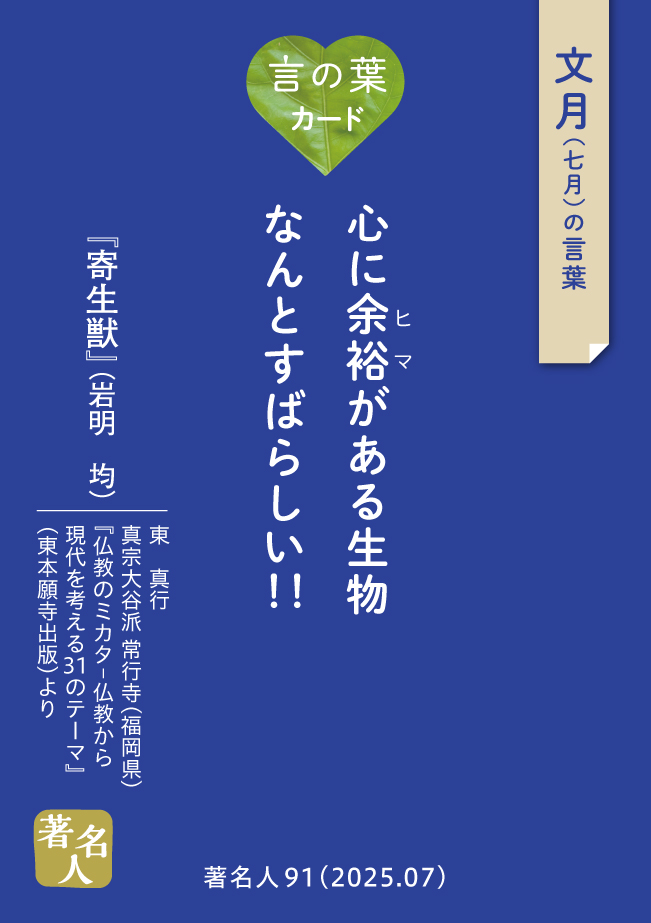
岩明均(いわあきひとし)『寄生獣(きせいじゅう)』(新装版第10巻、最終話)に、こんな問答があります。
「道で出会って知り合いになった生き物が ふと見ると死んでいた そんな時 なんで悲しくなるんだろう そりゃ人間がそれだけヒマな動物だからさ だがな それこそが人間の最大の取り柄(え)なんだ 心に余裕(ヒマ)がある生物 なんとすばらしい!!」。
実際の生き物ならまだしも、創作物にあらわれる登場人物たちは、実世界には存在しません。しかし、私たちは物語を通して、その実在を強く感じることがあります。私たちの心の余剰が、たとえ目先の忙しさのなかで搔(か)き消えそうになっているとしても、そうさせるのです。
過ぎ去る日常を生きる私たちにとって、あわただしさのなかで日々のきめ細やかさを味わい、他者と深く共感することは稀(まれ)かもしれません。しかし、私たちの日々を、他者の存在を表現によってなぞり、再現によって再確認する。それによって初めて私たちは、日々の重さを知り、存在そのもののかがやきを見出(みいだ)すのではないでしょうか。
文学であれば文脈が、マンガであればコマ割りが、アニメであれば動きが、私たちに日々のいぶきを、存在のかけがえのなさを回復させます。創作者の胸中(きょうちゅう)にあらわれたいのちが表現によって再現されるとき、そのいのちを実感するのはむしろ、日常の中で見失っている私たちの方なのです。
『寄生獣』(岩明 均)
東 真行氏
真宗大谷派 常行寺(福岡県)
『仏教のミカタ-仏教から現代を考える31のテーマ』
(東本願寺出版)より
著名人 2025 07