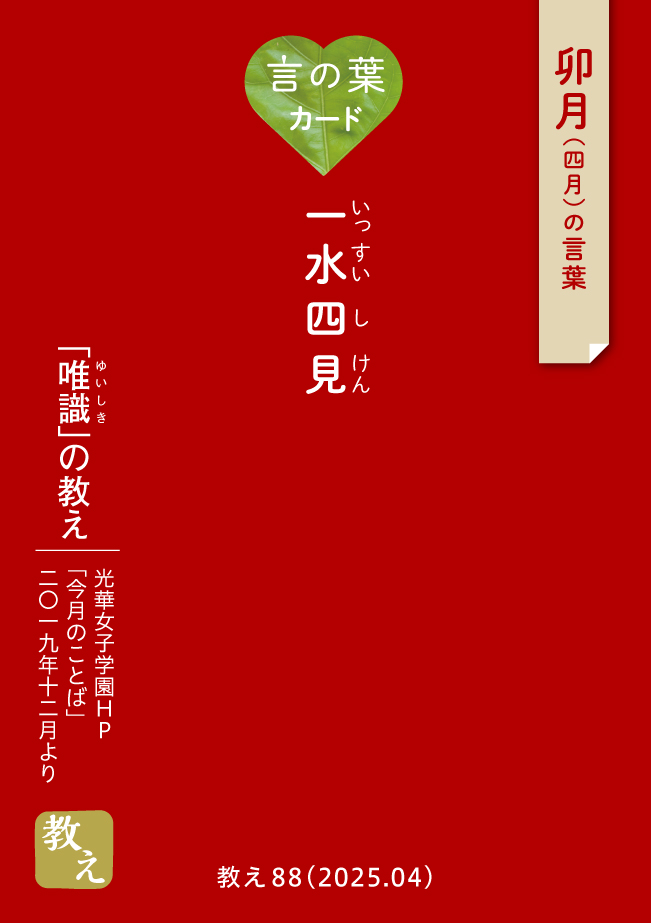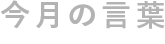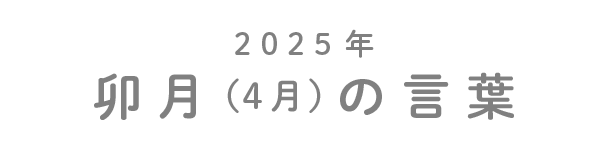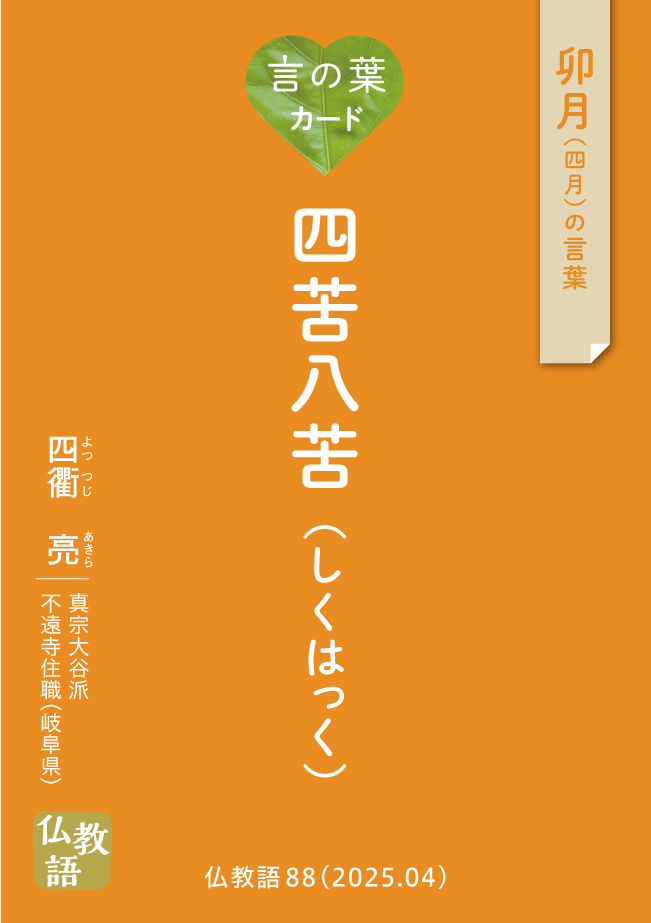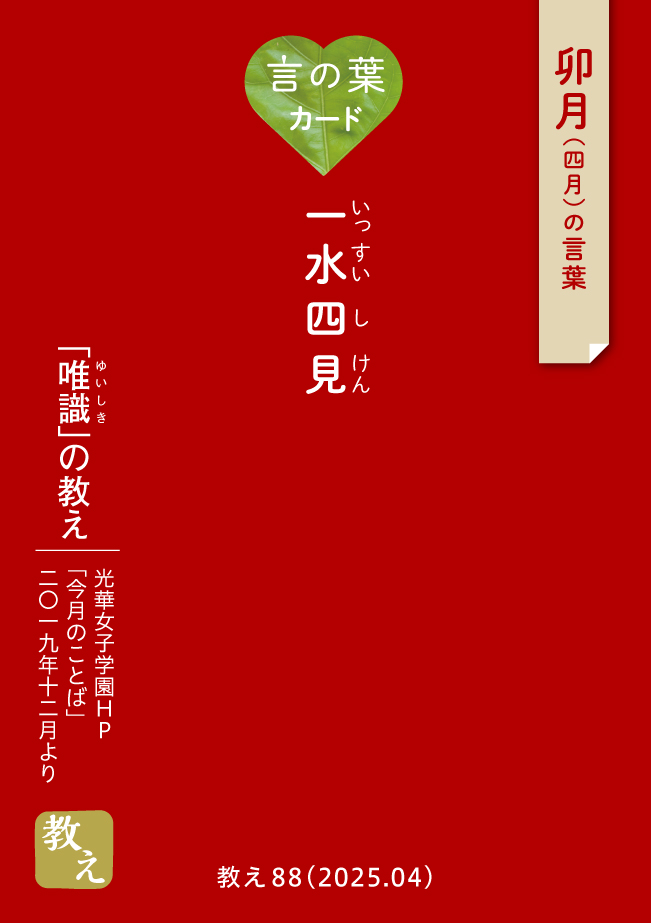
さまざまな苦しみや悩みから脱却するためには、正しいものの見方が大切です。しかし、人間は、正しいものの見方をすることはなかなか難しいと思います。学校や会社の中でも、あるいはグループにおいても、一人でも気にいらない人がいると落ち着かないという経験があると思います。しかし、そこには単に「その人」がそこにいるだけです。結局のところ「嫌い」という私自身の心が「あの人さえいなければいいのに」という見方に傾いていき、そこから苦しみが生まれてくるわけです。そうすると、互いに傷つけ合い、最後には苦しみ合う結果になってしまうのです。
「認識の主体が変われば認識の対象も変化する」
仏教の考え方の一つ『唯識(ゆいしき)』に「一水四見(いっすいしけん)」という言葉があります。一口に水といっても四つの見方に見える。つまり、同じものでも見る立場や心のもちようによって違うように見えてくるという意味です。
① 天人には水がきれいに透き通ってガラスのように見える。
② 人間の私たちには、そのままの水に見える。
③ 魚たちには住み家と見える。
④ 餓鬼(がき)には燃えた血膿(ちうみ)に見える。
これは「天人」「人間」「魚」「餓鬼」という立場で「水」を見た場合、それぞれ異なって見えることを例えたものです。これを私たちに当てはめてみると、私たち人間は、みんな生まれ育った環境や境遇、受けた教育、経験したことや考えてきたこと、興味を持ったことなどさまざまで、それぞれその人独自の世界観があり、価値観があります。それが大きなひとつの「ものさし」となって、いろいろなことを認識しています。
それでは、自分が見ている世界は、他人から見てどのように見えるのでしょうか。同じものを見ていても、気づかないことがあるのではないでしょうか。
世界というのは、実は同じ一つの世界にみんながいるのではなく、それぞれがそれぞれの世界を作り上げて、それぞれの世界を見ているということです。つまり、人それぞれが各々の世界をもっていて、どこかの接点で互いの世界を共有しています。そこから「つながり」が生まれてくるわけです。
人生の中で、いろいろな苦しみや悩みに出合った時、ものの見方を私自身が変えることによって、見えなかったものが見えたり、気づかなかったことに気づかされたりして、世界が拓(ひら)かれていくのだと思います。
「唯識」の教え
光華女子学園HP「今月のことば」
(2019年12月)より
教え 2025 04

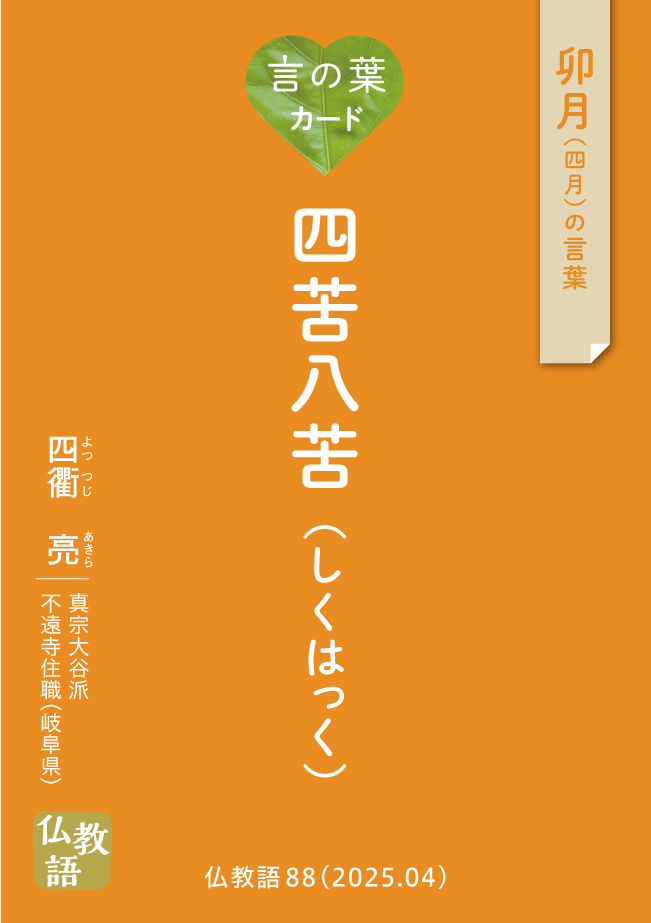
「この仕事を成し遂げるのはたいへんだった、本当に四苦八苦した」という言い方で使われることがある「四苦八苦」。生(しょう/生まれること)・老(ろう/老いること)・病(びょう/病むこと)・死(し/死すること)の「四苦」に、愛別離苦(あいべつりく/愛する者と別れる苦)・怨憎会苦(おんぞうえく/怨み憎む者と会う苦)・求不得苦(ぐふとくく/求めても得られない苦)・五陰盛苦(ごおんじょうく/この世に存在することの苦)の四つを加え「八苦」と表します。それが説話集で解説され物語に使われて、この上ない苦しみを表す言葉として使われるようになりました。
生まれることも死ぬことも、自分ではどうしようもないことです。だから仕方がないと生きていくかというと、それだけで人生を終わらせたくないと思うから、「生苦」や「死苦」を感じます。いつまでも若く元気でありたいと考えて、アンチエイジングの情報があふれているのは、「老苦」の裏返しでしょう。様々な健康法や健康食品があふれているのも、病や死への畏(おそ)れが私たちを捉えているからではないでしょうか。
愛する者との別れを悲しみ悼(いた)む心が、たくさんの詩歌を生み出し、民族や国、時代を越えて伝わり響きます。憎しみや求めてやまない心が物語を生み出すこともありますが、それだけでは済まず、激しい争いと戦い、殺戮(さつりく)の歴史を今も作っています。
生や死の苦しみを感じなければ「楽」になれるのでしょうか。いつまでも若く病むこともなければ「楽」でしょうか。憎む相手を打ち負かせば「苦」が消えて「楽」になり、求めていた物が手に入れば「楽」になるのでしょうか。気に食わない相手は、次々と出てきます。手に入れば別の物が欲しくなります。私たちは、いろんな原因と条件を縁として生きています。それを全て思い通りにしようと力んで、苦を楽にしようとします。それが更なる「苦」を生むのです。
「一切皆苦(いっさいかいく)」。人間の生き方が「苦」を生むのです。「苦あれば楽あり」の全てが「苦」であるということが、仏様の教えです。楽を求めて、まず私が楽になろうとあがくことが「苦」をもたらしていたと目覚めたのです。その目覚めは、全ての人に通じる目覚めです。
四衢 亮(よつつじ あきら)氏
真宗大谷派 不遠寺住職(岐阜県)
仏教語 2025 04


「私」というところに立ちますと、この人生はどう考えても理不尽なものですね。思い通りになれば理不尽とは言いません。しかし、誰もかれもこの人生については理不尽なものを感じています。「なぜ?」「どうして?」という疑問を胸の奥深くに持ちながら、我々は生きています。だから、どう考えても納得できないのです。
自分の人生にどうしても納得がいかない。特に戦前、戦中、戦後と生きられた方にとっては、いかに娑婆(しゃば)とはいえ納得しきれないものがいっぱい胸に残っていると思うのです。「これが娑婆だ」、「これが人生だ」と言ってみましても、この私というものを納得させるわけにはいかないのですね。そういうものが、私どもの中にあります。
そうしますと、この「私」というのは、正体がはっきりしないものなのです。「私、私」と言い続けておりながら、そして他でもないこの「私」が生きてきたにもかかわらず、この「私」に納得できないということは、「私」という存在がわからないからです。
我々は「私」を依りどころにし、「私」を中心として生きているけれども、その私は実は正体不明なのでしょう。ということは、最期には「わからん」と言って死なねばならないのです。「こんなはずではなかった」というのは、私がわからんということですね。
この、わからんままに人生を終わっていくことを「流転(るてん)」というわけです。本当に、人生にきりがついたというわけにはいかないのです。きりがないのです。これで完了した、これできりがついた、ということがないのですね。
平野 修氏
九州大谷短期大学元教授
『本尊の意義をたずねて』
(東本願寺出版)より
法話 2025 04


私は『サンガ』の「分断の手当て」という連載の中で、「大きな主語」ではなく「小さな主語」を皆さんに届けたいと思っています。連載ではいつも、「○○さんは」という固有名詞、名前が挙がるような記事を心がけているんですが、固有名詞で語ろうと思うと、やはり現場に行かなきゃいけないんですよね。現場に行かないと、「○○さんは」とは言えないわけです。
そういった意味でも、メディアで発信をする一人として、絶対に現場に行かなければいけないと感じています。つい先日行ったパレスチナのヨルダン川西岸地区、ジェニンという場所でも、やはりパレスチナという大きな主語では語られない、厳しい現状が目の前に横たわっていました。
大きな主語がぶつかり合うと、何の救援もない中で、当事者同士が孤立感だけを深めていきます。大衆は非常に冷たいですから、関心がなくなれば、また他のテーマに関心を移し、何も解決しないまま去っていってしまう。そういうことが繰り返されてしまうんですね。
人々の「Aだろう」、「いや違う、Bだろう」というような対立のなれの果てに、排除、排斥、憎しみの連鎖が生まれます。そのような大きな主語ではなくて、小さな主語で語ることによって、初めてお互いが協力し合える、その接点を見いだすことができるんだと思います。
堀 潤氏
(ジャーナリスト・キャスター)
第17回「親鸞フォーラム」より
著名人 2025 04